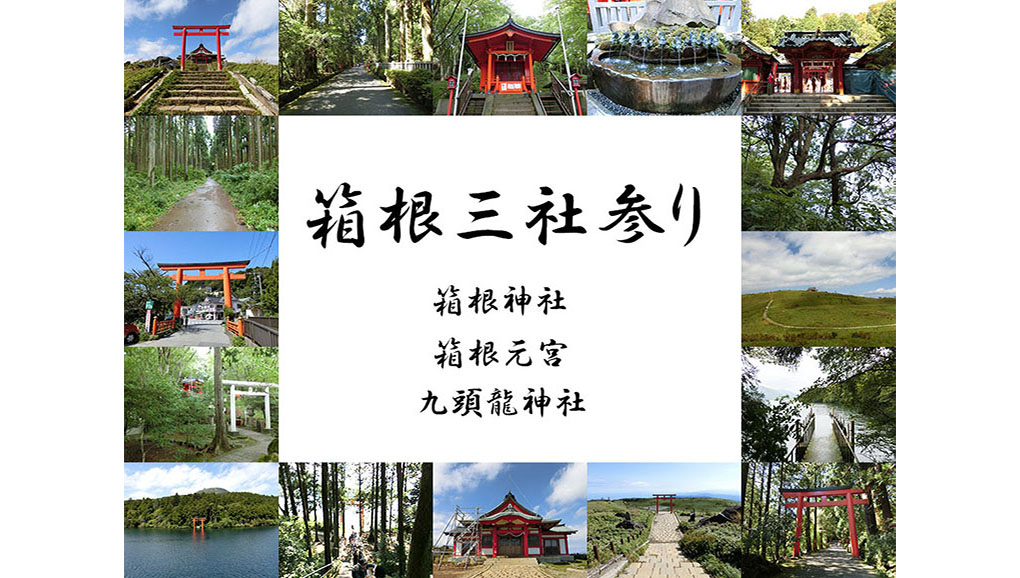渋谷区にある豊栄稲荷神社の参拝レポートです。
読み方は「とよさかいなりじんじゃ」です。古くから渋谷のお稲荷さんとして信仰されてきた神社で、境内には十三基の庚申塔があります。金王八幡宮のすぐお隣、渋谷警察署の裏手に鎮座しています。最寄駅は各線の渋谷駅になります。
序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。
渋谷の「豊栄稲荷神社」へ
この日は嫁と二人で渋谷駅周辺の神社巡りに出掛けてきました。
季節は8月下旬の真夏の神社巡りです。気温が35度近くあるという、とにかく暑い中での散策です。
参拝を予定している神社は全部で9ヶ所。全て渋谷駅の周辺です。
とは言え、9ヶ所の神社が全て密集しているわけではなく、駅の周辺に点在している形ですので、灼熱の気温の中をそれなりに歩く覚悟は必要です。
しかも台風が接近しているとのことでして、夕方からは雨になる可能性もあり、できれば午前中には回り終えたいと。
ここまでくると、神社巡りがじゃっかん修行のように思えなくもありません。
自分たち的には、楽しい散策という意識なんですけどね。
こちらの記事で紹介する豊栄稲荷神社は、そんな灼熱の神社巡りの中で、4ヶ所目に訪れた神社です。
本当は3ヶ所目に訪れる予定だったのですが、うっかりミスで順番が入れ替わり、4ヶ所目になりました。
豊栄稲荷神社から細い道路を挟んだすぐ向かい側には、金王桜でも有名な金王八幡宮があり、豊栄稲荷の御朱印は金王八幡宮の授与所にて頂けるんです。なので僕たちは、先に豊栄稲荷に参拝し、その後金王八幡宮に向かい、その二社の御朱印を頂こうと目論んでいました。
「御朱印というのは参拝してから頂くものだ」と僕も嫁も思っていますので、それが順序かな~と。
しかし、うっかりと先に金王八幡宮に立ち寄ってしまったんです。
まさにうっかりです。うっかり八兵衛です。
そしてそのままの勢いで、金王八幡宮の授与所にて、参拝前の豊栄稲荷の御朱印も頂いてしまったんです。
「御朱印というのは参拝してから頂くものだ」なんて、もう偉そうには言えません。
しかも豊栄稲荷の読み方は、本来「とよさかいなり」なのに、勝手に「ほうえいいなり」だと思っておりまして、御朱印を頂く際にも「ほうえいいなりの御朱印もください」なんて堂々と発してしまって…。
お恥ずかしいのは仕方ありませんが、豊栄稲荷神社に対して、なんだか失礼なことばかりしてしまっている気がします。
本当にすみません。
ですのでそんな謝罪の気持ちも込めて、豊栄稲荷には参拝することにしました。
金王八幡宮の西側の参道から境外に出ますと、目の前が豊栄稲荷です。
先に御朱印を頂いてしまったこと、社名の読み方を間違えてしまったことを、一刻も早く謝りたいと、早足にて入口の鳥居へと向かいます。
ご由緒
ご祭神は、五穀豊穣の神様、穀物や食物の神様である、宇迦之御魂命(うかのみたまのみこと)です。倉稲魂命とも表記され、稲荷神と同一です。
創建は鎌倉時代です。氏族であり渋谷という地名の元にもなっている、渋谷氏により創建されたと伝えられています。当初は現在の渋谷駅の近く、かつて渋谷川が流れていた辺りに鎮座していました。渋谷川が渋谷城の壕に使われていたため、「堀ノ外稲荷」と称されていました。その後、川の端にあったことから「川端稲荷」、また、由来は不明ですが「田中稲荷」とも称されるようになったそうです。
一方、猿楽町(山手線の西側)にはかつて但馬豊岡藩京極家の下屋敷があり、屋敷内には豊澤稲荷神社が祀られていました。明治初年にはこの豊澤稲荷が付近の稲荷を合祀し、道玄坂に遷座します。
その後、豊澤稲荷が田中稲荷に合祀され、昭和36年に区画整理事業に際し、金王八幡宮と隣り合う現在の地に遷座し、豊栄稲荷となりました。
形を変えつつも、古くから渋谷のお稲荷さんとして、厚く信仰されている神社です。
境内には十三基の庚申塔もあります。
境内案内
金王八幡宮の西側の鳥居から境外に出ますと、目の前に見えるのが豊栄稲荷神社になります。左手が入口のようですので、そちらに向かいます。

こちらが豊栄稲荷神社の正面入口になります。石鳥居の向こうには赤い鳥居が連なっているのが見えます。

石段を上がり、石鳥居の前へ。中央には百度石がありました。

一礼して鳥居をくぐり境内へ。

参道は少し右に折れて延びています。赤い鳥居が連なる景色は綺麗です。

左には境内にある庚申塔群の説明が書かれていました。

その先に手水舎です。手水舎の赤も綺麗です。

お清めをします。

お清めを終え、赤鳥居の参道に戻ります。

境内の右手に並んでいるのが、十三基の庚申塔です。三猿が刻まれたものが多いです。

赤鳥居の中を進みます。

鳥居を抜けると、正面に赤と白の社殿です。

左には授与所と思われる建物がありますが、閉まっています。

右には神社ご由緒を記した石碑と、庚申塔の略記です。その脇からも境内には出入りできるようになっています。

拝殿へと進みます。拝殿前にはお狐さん。

こちらが左のお狐さんです。

こちらが右のお狐さん。どちらも怖い顔をしています。

参拝します。扁額は明治神宮の宮司さんが書かれたものでした。

拝殿の中にも扁額が見え、豊栄稲荷の元となった、二つの神社の名が記されています。

拝殿を振り返るとこんな感じです。

境内の左手には「蔵修館」と書かれた建物があります。剣道場のようです。

赤鳥居の綺麗な境内にてしばらく過ごし、豊栄稲荷神社を後にしました。

参拝を終えて
先に御朱印を頂いてしまったり、社名の読み方を間違えていたりと、失礼を重ねてしまった豊栄稲荷ですが、無事に参拝することができました。
境内は広くはありませんが、入口から社殿に向かい赤い鳥居が連なっていて、とても綺麗です。
都内の神社でも赤い鳥居が連なっているところは、海外からの観光客の方などが大勢写真を撮ったりしているのをよくお見掛けしますが、豊栄稲荷は静かなものでした。参拝者の姿もちらほら見掛ける程度でして、境内にはほとんど人がいない状態でした。
赤い鳥居を抜けた先には、お狐さんが守る赤を基調とした綺麗な社殿です。
周囲には赤い提灯も連なって掛けられていて、豊栄稲荷は全体的に「赤」のイメージが強かったです。
夏でしたので木々の緑も綺麗で、緑の中に余計に赤が映えていて、素敵な境内でした。
暑さに耐えつつ、時間をかけてゆっくり参拝させて頂きました。
境内の右手には、十三基の庚申塔が並んでいます。彫られているものや形は様々だったのですが、三猿を彫ってあるものが多かったです。
神社巡りをしていますと、庚申塔というものをよく見掛けます。
にも関わらず、僕はまだ庚申塔というのが何なのかちゃんと理解していなかったので、この機会に勉強してみました。
ざっくりですが、庚申塔は中国から伝来した道教に由来するもので、「庚申信仰」に基づいて建てられた石塔とのこと。道教が日本の様々な信仰と結びついて浸透していったため、神社にも庚申塔が多く建てられているみたいです。
庚申塔の「申」が干支では猿を表すため、三猿などが彫られたものが多いそうです。
また、「道ひらき」の神様である猿田彦命や、道祖神とも結びつき、道しるべの役割を持って建てられた庚申塔も多いそうです。
なるほど。
これまで何度となく庚申塔を目にしていながら、初めて知ることばかりです。お恥ずかしい。
まだまだ浅い知識ではありますが、今後は庚申塔を見掛けたら、今までよりは少し違った視点で見ることができそうです。
庚申信仰については、けっこう難しくてまだまだちゃんと理解するには程遠いですけれど。
少しずつ賢くなりたいと思います。
豊栄稲荷ではもう一つ気になったものがあります。境内の左手に「蔵修館」という建物がありまして、ドアには「使用の前後は神様に感謝の心をこめてご神前に拝礼しましょう」と書かれたりしています。
その場では何の建物なのかわからなかったのですが、帰宅後に調べましたところ、どうやら剣道場のようです。
境内に剣道場がある神社というのは、僕は初めて訪れました。
僕たちの参拝中は閉まっていて稽古の声など聞こえなかったのですが、道場の声を聞きながら参拝というのも、また風情がありそうですね。
豊栄稲荷神社、参拝できて良かったです。
この後僕たちは、宮益坂にある「宮益御嶽神社」へと向かいます。
御朱印
こちらが豊栄稲荷神社の御朱印です。

御朱印の受付時間
豊栄稲荷神社の御朱印は、向かいにある金王八幡宮の授与所で頂くことができます。御朱印と御守りを頂ける時間は、9時30分から16時30分までです。
(※お時間やご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)
アクセス
住所は東京都渋谷区渋谷3-4-7です。
豊栄稲荷神社の公式サイトはありません。
電車
各線 「渋谷駅」から徒歩5~7分。
東口方面です。渋谷警察署の脇に出て、渋谷駅を背にして首都高の右側を東に進み、少し先の路地を右折です。
駐車場
参拝者用の駐車場はありません。近くにコインパーキングがいくつかあります。
周辺のパワースポット
渋谷区の神社一覧