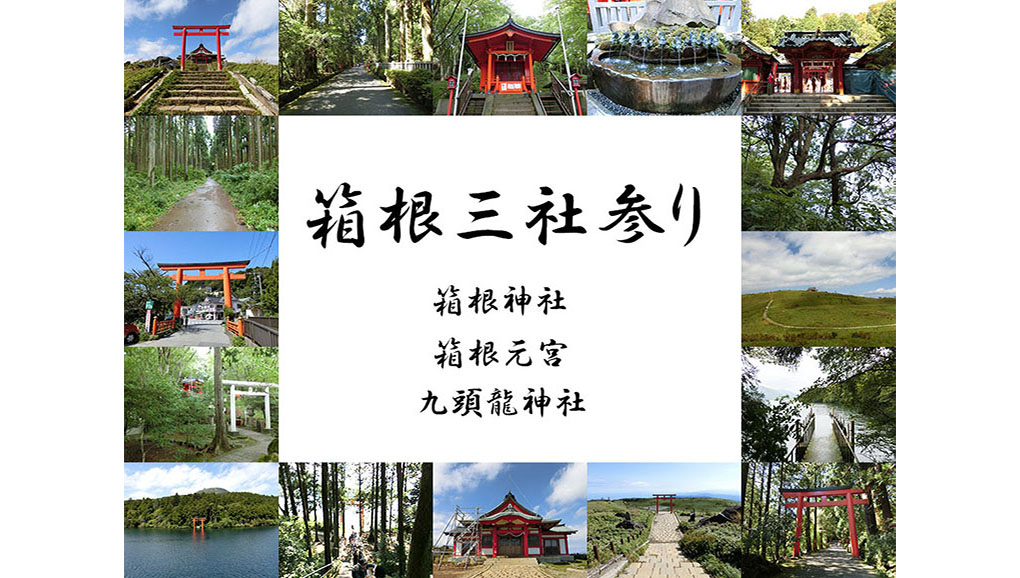諏訪大社という社名は、多くの方が一度は見聞きしたことがあると思います。
しかし諏訪大社が一つの神社ではなく、四つの宮から成り立っていることは意外と知られていないかもしれません。
四か所に鎮座はしていますが、どこもそこまで離れてはいませんので、じゅうぶん一日で回れる範囲内です。
こちらの記事では、諏訪地方の出身である著者が、それぞれの宮の見どころと、四社巡りの順番やお勧めのコース、御朱印、アクセス、周辺情報などを紹介しています。
諏訪大社は4つの宮の総称
諏訪大社は、長野県の諏訪地域にある神社で、全国に一万社以上あると言われている「諏訪神社」の総本社です。
大変歴史の古い神社で、日本最古の神社の一つとも言われています。
諏訪地域とは、諏訪湖の周りにある「諏訪市、岡谷市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村」の6市町村を指し、地図ですと下の赤い場所になります。

(画像出典:ja.wikipedia.org)
赤い地域の中、小さく水色になっているのが諏訪湖で、諏訪大社は諏訪湖を中心にして4ヶ所にある神社の総称です。
四つの宮の名称は以下になります。
- 上社前宮
- 上社本宮
- 下社春宮
- 下社秋宮
「上社」と「下社」に分かれていて、上社には「前宮」と「本宮」、下社には「春宮」と「秋宮」がある形です。上社と下社は同格です。
本来のご祭神は諏訪地方の土着の神々であるという説もありますが、現在のご祭神は、大国主命の御子神である建御名方神(たけみなかたのかみ)と、その妃である八坂刀売神(やさかとめのかみ)です。
創建の年代は不明ですが、武甕槌命との相撲に敗れた建御名方命が諏訪の地に逃れ、以後は他の土地へ出ないことを誓ったのが起源とされています。
軍神としての性格が強く、平安時代には坂上田村麻呂が戦勝祈願を行ったとされ、鎌倉時代には源頼朝が神馬を奉納し、戦国時代には武田信玄により厚く崇敬されました。武田信玄は戦の際には、「南無諏訪南宮法性上下大明神」の旗印を先頭に、諏訪法性兜をかぶって出陣したと伝えられています。
七年に一度行われる、大きな柱を曳き、山から落とし川を渡る「御柱祭(おんばしらさい)」は天下の奇祭と言われ、日本三大奇祭のひとつにも数えられています。
諏訪大社に纏わる不思議な伝説は数多くあり、強力なパワースポットとしても有名です。
また、都市伝説の域ではありますが、古代イスラエルとの関係も度々取り上げられる神社でもあります。
諏訪信仰の総本社として、厚く信仰されている神社です。
見どころと詳細
私事にはなりますが、僕は現在東京在住なのですが、出身が諏訪大社のある諏訪地域でして、生まれも育ちも、大社のお膝元である茅野市というところです。
初宮参りに始まり、七五三や毎年の初詣も諏訪大社。大人になってからは、諏訪大社の本宮にて結婚式も挙げております。七年に一度行われる御柱祭にも参加していました。
こちらは平成28年の御柱祭で撮った写真です。


そんな個人的に小さい頃から馴染みのある諏訪大社ですが、こうして神社巡り記事を書くようになった今、四社ともとっても素敵な神社であることを、改めて感じております。
四社それぞれどんな神社なのか、各記事で詳細をまとめていますので、まずはどんな感じなのかを、ざっくりでもいいので見て頂き、少しでも興味を持って頂けたらと。
境内の様子もかなり細かく紹介していますので、わかりやすいかと思います。
上社・前宮
上社・本宮
下社・春宮
下社・秋宮
四社巡りの順番
四つの宮はそれぞれ違った魅力がありますし、どこも素敵な場所ですので、諏訪大社に参拝するのでしたら、やはり四社への参拝をお勧めします。
僕の場合は地元が諏訪地域ですし、何度かに分けて四社を巡ることも簡単ではありますが、観光なので訪れる方は、できれば一日で回ってしまいたいですよね。
ではまず、四つの宮の位置関係を見てみましょう。
上社の前宮と本宮は近くにあります。
同じく下社の春宮と秋宮も近くにあります。
ですので必然的に、上社の「前宮と本宮」がワンセット、下社の「春宮と秋宮」がワンセットになり、上社から回るか下社から回るか、のどちらかになるかとは思います。
四社巡りは特に回る順番が決められているわけではありません。自由です。
ただ、上社の場合には、まず前宮に参拝してから本宮へ、という説もあるみたいです。地元民である僕の父親がそう言ってました。
僕もそれに倣って上社は前宮から本宮、という順番で参拝をしましたが、それぞれが回りやすい順番で問題ないと思います。
四社へのアクセス
こちら、諏訪大社が発行する四社参り冊子に載っている、それぞれの宮へのアクセスです。

(画像出典:suwataisha.or.jp)
それぞれの最寄り駅は、春宮と秋宮が下諏訪駅、前宮と本宮が茅野駅ですが、本宮は上諏訪駅からも行くことができます。 それらを踏まえ、以下に交通手段別のアクセスを紹介していきます。
車(レンタカー含む)
諏訪大社の4社を巡るのでしたら、車で回るのが一番てっとり早いです。楽です。
それぞれの宮には広い駐車場がありますので、その点でも安心です。
高速ですと、上社なら中央道の諏訪IC、下社なら同じく中央道の岡谷ICが最寄です。
諏訪湖に近いのは下社の方です。蓼科や八ヶ岳に近い方は上社です。観光地ですし温泉地でもありますので、諏訪大社以外にも何かと楽しめるスポットはあるかと思います。
茅野駅、上諏訪駅には駅にレンタカーがありますので、現地からレンタカーといいのも手かと思います。下諏訪駅にも少し歩いたところにあります。
電車&タクシー
一方、車がないと四社参りは少々大変にはなります。
交通費での出費をそこまで気にしないのであれば、タクシーで回るのが最も楽です。駅にはタクシーが待機していますし、各お宮で待機タクシーがいなかった場合でも、配車をお願いすれば、そこまで待たされずに乗れるかと思います。
予算に余裕があるのでしたら、貸し切りで四社巡りをしてくれるタクシー会社さんもありますので、そちらが一番楽です。
例えばこちらですと、15,000円~23,000円ほど。お値段もリーズナブルではないかと。
四社全てを1台のタクシーで回るのが当然最も楽ではありますが、少しでも節約するのでしたら、電車とタクシーの併用がお勧めです。
上社の前宮と本宮の最寄り駅は「茅野駅」で、下社の春宮と秋宮の最寄り駅は「下諏訪駅」ですので、茅野駅からタクシーで前宮と本宮を回り、再び茅野駅へ。そして電車で2駅先の下諏訪駅まで行き、そこから新たにタクシーで春宮と秋宮へ。そんなコースもお勧めです。
電車&バス
タクシーを使わないとなると、駅からバスでの四社巡りが一番無難ではありますが、四社巡りのバス事情が、実はとっても不便なんです。
上社の場合ですと、以前は茅野駅から前宮へのバスがあったのですが、現在は廃止されています。ゆえに、茅野駅から前宮にはタクシーを使わざるを得ませんが、本宮でしたら上諏訪駅から「かりんちゃんバス」というので行けます。逆に本宮からも上諏訪駅に行けます。かりんちゃんバスの公式サイトは以下です。
上記サイト内の、市内循環(1)内回り線(2)外回り線(3)すわ外周線(8)有賀・上社統合線で行けます。上諏訪駅の霧ヶ峰口or諏訪湖口から乗車(乗り場は路線により違いますのでご確認を)し、「上社」バス停下車です。
一方、下社ですと、秋宮、春宮ともに下諏訪駅から「あざみ号」という循環バスで回れます。あざみ号の公式サイトは以下です。
下諏訪駅から乗車し、秋宮は「諏訪大社秋宮前」、春宮は「諏訪共立病院前」or「万治の石仏」下車です。
まとめますと、春宮と秋宮は下諏訪駅からバスで行けます。本宮も上諏訪駅からバスで行けます。
ただし本宮と前宮の間のバスもありませんし、上諏訪駅や茅野駅から前宮のバスもありません。
バスでの四社巡りを検討している方は、タクシーとの併用が必須です。
電車&徒歩
歩くのが好きな人でしたら、かなりの距離は歩くことになりますが、一部徒歩での移動も可能です。
もちろん四社全部歩いて回ることもできなくはないですが、それはかなり大変かと。
個人的な判断ですが、徒歩圏内かと思うのは以下の間です。
①前宮 - 本宮 (徒歩約25分)
②下諏訪駅 - 秋宮 (徒歩約15分)
③秋宮 - 春宮 (徒歩約15分)
④春宮 - 下諏訪駅 (徒歩約20分)
どれもそこそこ歩くことにはなりますが、歩けない距離ではないので、足と時間に余裕のある方には、ありだとも思います。
それでは次の項にて、僕のお勧めの回り方を紹介します。
おすすめコース
先ほども記載しましたが、一番楽なのは車で回る方法です。
その次に便利な回り方は?と聞かれましたら、以下のようなコースでお勧めしたいです。
時短コース
できるだけ短い時間で4社巡りをしたい、という方には以下のコースが最適かと思います。
茅野駅→(タクシー)→前宮→(タクシー)→本宮→(タクシー)→茅野駅→(電車)→下諏訪駅→(タクシー)→秋宮→(タクシー)→春宮→(タクシー)→下諏訪駅。
基本はタクシーで回るコースです。タクシー代を気にしないのであれば、電車移動の部分もそのままタクシーで行ってしまう方が楽チンではあります。上社~下社は車で約30分前後です。待機タクシーがいない場合、それぞれの宮でその都度タクシーを呼ばなければいけないというデメリットはありますが、一番楽には回れます。その都度タクシーを呼ぶのが面倒でしたら、タクシー料金は高くなってしまいますが、参拝の間待ってもらう形にはなります。
のんびりコース
時間を気にせず、のんびりと4社巡りをしたい、またはタクシー代にそこまで掛けたくない、という方には以下のコースがお勧めです。
茅野駅→(タクシー)→前宮→(徒歩約25分)→本宮→(タクシー)→茅野駅→(電車)→下諏訪駅→(徒歩約15分)→秋宮→(徒歩約15分)→春宮→(徒歩約20分)→下諏訪駅。
もしくはバスのタイミングさえよければ、本宮→(かりんちゃんバス)→上諏訪駅→下諏訪駅という手段でもOKです。かりんちゃんバスの時刻表はこちらです。
歩くのが苦ではない人でしたら、上記のような形で「午前中は上社、午後は下社」というように時間を掛けて回るのもお勧めです。前宮と本宮の間には、諏訪大社に関連のある神社や、「神長官守矢史料館」などもあります。
裏技コース
なんと、無料の送迎バスで4社を回れてしまうという裏技があります。
それは「上諏訪温泉しんゆ」というホテルが行っている、宿泊者限定のサービスです。姉妹ホテルの「萃(すい)」の宿泊でも加納です。
午前と午後の一日2回、4社をバスで回ってくれます。しかもガイド付きで。それぞれの宮での出発時間、到着時間が決まっていますので、自分のペースでのんびりと、というわけにはいきませんが、嬉しいサービスではあります。
宿泊者限定ですので、泊まらないといけないですけどね。以下のサイト内に詳細が掲載されています。
https://xn--sui-suwako-y83i.jp/worship/
以上、おすすめのコースを3つ紹介してみました。
今後はもっと回りやすい手段ができたらいいですね。その際には改めて追記させて頂こうと思います。
御朱印と記念品
諏訪大社の四社でそれぞれ御朱印を頂きますと、最後に頂いた場所で、素敵な記念品を頂くことができます。
御朱印帳に諏訪大社の御朱印が並んでいれば、対応してくださる方も「四社目だ」とわかるかとは思うのですが、御朱印帳を出す際に一言、四社目であることをお伝えしましょう。
僕の場合は四社のうち最後に訪れたのは下社の春宮でしたので、そちらで頂きました。
記念品は「栞」と「そば落雁」でした。

栞はまだ使用しておりませんが、そば落雁は美味しくて、12個入りをあっと言う間に食べてしまいました。
なかなか落雁を食べる機会もなかったのですが、そば落雁って美味しいですね。日本茶に素晴らしく合います。
さらにこの諏訪大社の落雁は、一枚一枚に神紋が描かれていました。
諏訪大社の神紋は「梶」で、上社と下社でほんの少し違うんです。左が下社の御神紋で、右が上社の御神紋です。

落雁には、どちらの神紋も同数入っていました。
記念品で落雁を頂きましたら、是非食べる前に見てみてください。
(追記:現在の記念品は、落雁と栞から、「特製きんちゃく(巾着袋)」へと変更になっています。今後も変更される可能性がありますので、ご了承ください。)
御朱印については各神社の記事で詳しく紹介していますが、以下に四宮の御朱印を掲載させて頂きます。
左上が上社本宮、右上が上社前宮、左下が下社春宮、右下が下社秋宮になります。

周辺のパワースポット
諏訪大社は強力なパワースポットであり、数多くの伝説も残されています。
そして周辺には、諏訪大社と関わりの深い場所、神社などが数多く存在しています。
その中でも、僕が記事にしている場所を数か所、こちらで紹介しておきたいと思います。
神長官守矢史料館
諏訪大社上社と関わりの深い資料館で、江戸時代まで上社の神長官を務めた守矢家の敷地内にあります。館内には上社の神事である「御頭祭(おんとうさい)」の展示、敷地内には、諏訪大社の起源とも考えられている「御左口神(ミシャグジ神)」を祀る社もあります。前宮と本宮のちょうど間くらいにあります。なかなか凄いところですので、是非訪れてみてください。
北斗神社
上社本宮のすぐ近くにある神社で、山の中へと真っ直ぐに延びる、200段の石段でも有名な神社です。石段は最大傾斜角度45度、長さは160メートルで、その道のりはスリル満点です。寿命の神様としても信仰されている神社です。
八劔神社
諏訪大社上社の境外摂社で、諏訪湖に氷の亀裂が走る御神渡り(おみわたり)を検分する、御渡神事(みわたりしんじ)を行うことでも知られている神社です。かつては諏訪湖中に突き出た高島の里と呼ばれる地に鎮座していました。
手長神社
諏訪大社上社の境外摂社で、足長神社とともに巨人伝説の残る神社です。かつては手長足長の巨人(ダイダラボッチ)を祀っていたのではないかとも考えられています。映画『君の名は』の宮水神社のモデルとなった神社の一つとも言われています。
足長神社
諏訪大社上社の境外摂社で、手長神社とともに巨人伝説の残る神社です。参道の入口には巨木が聳え、足長神社の御柱祭では、境内へと続く急な石段を、大きな柱がいっきに引き上げられていきます。
葛井神社
茅野市にある上社の末社です。境内にある「葛井の清池」は諏訪大社上社の七不思議の一つにも挙げられている場所で、抜け穴伝説のある池です。葛井の清池に投げ込んだものが、静岡にある「さなぎの池」に浮かび上がるとも言われています。
多留姫神社
名勝として茅野市の文化財にも指定されている「多留姫の滝」がある神社です。多留姫の滝には、滝壺に椀や糠を流すと、葛井神社の「葛井の清池」に浮かぶという言い伝えがあります。周辺は「多留姫文学自然の里」として、ハイキングなども楽しめるよう整備されています。
他にも諏訪大社に関係した神秘的な場所はいくつもありますので、記事にした際には、順次追加させて頂きます。
機会がありましたら、ぜひ諏訪大社4社参りと合わせて立ち寄ってみてください。