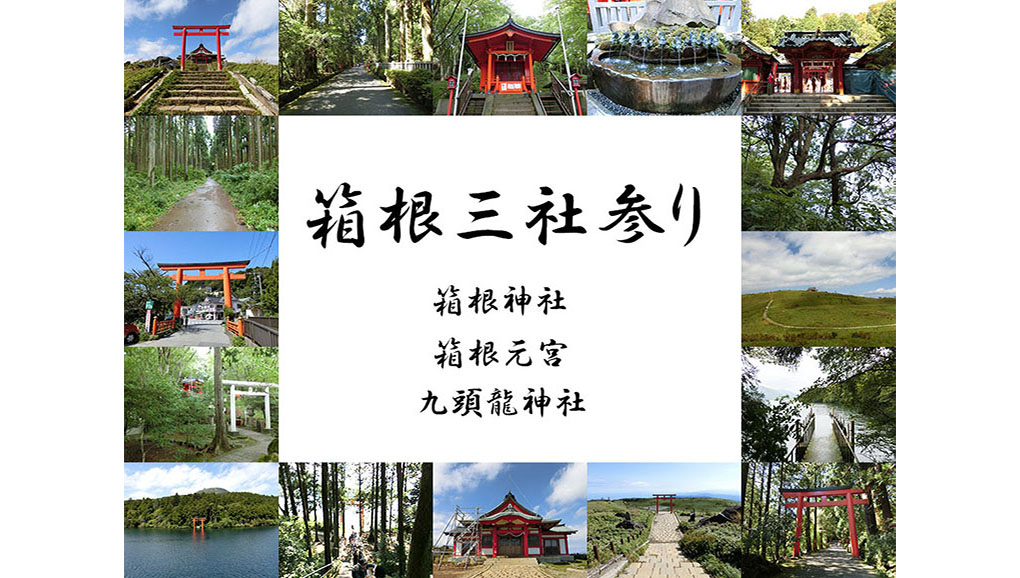熱海市にある伊豆山神社の参拝レポートです。
読み方は「いずさんじんじゃ」です。源頼朝が源氏の再興を祈願したといわれる神社で、後に妻になる北条政子と逢瀬の場でもあったことから、縁結びのご利益でも知られています。参道の入口には熱海の源泉である走り湯があります。来宮神社とともに、熱海を代表する神社です。
序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。
熱海の「伊豆山神社」へ
訪れたのは一月の中旬。それなりに寒い時期です。
僕たち夫婦は、毎年一月に温泉旅行に出掛けるのが恒例になっています。箱根、伊豆、草津、鬼怒川など関東近郊に行くことが多いのですが、今年はその行き先に熱海を選びました。
僕は子供の頃に家族旅行で熱海に行った覚えはあるのですが、大人になってからは一度もありません。嫁も若い頃に行ったきりとのこと。
熱海は最近人気のスポットともいわれていますし、以前からなんとなく気になっていた場所ではあります。
ですので今回、初の熱海旅行に行ってみることに。
さらには熱海には有名な神社が二つあるんですよ。伊豆山神社と来宮神社です。どちらも名前は聞いたことがあったのですが、もちろん訪れたことはありません。
ということで、今回の旅行は「熱海で温泉に入り、二つの神社を回る」というプランに決定です。かなりシンプルなプランではありますが。
一泊二日の日程ですので、そんなにあれこれとは回れないんですよね。僕たちの交通手段は電車とバスですし。
事前にコースをある程度決める段階で、嫁が二つの神社について色々と調べてくれました。
まず来宮神社は、樹齢二千年のでっかい大楠があるとのこと。僕もそれはテレビか何かで見た覚えがあり、是非その大楠をこの目で見たいです。駅からも近いようですし、問題なく行けそうです。
そして伊豆山神社ですが、こちらもバスで行くことができ、本殿には普通に参拝できるのですが…なんとそこから険しい山道を登った先に本宮があるとのこと。せっかくですので、できれば本宮にも参拝したいです。
しかしです。
その道のりはかなり険しく、片道で約一時間掛かるようです。もうこれはちょっとした登山です。
僕は秋に鎌倉と江ノ島の神社を一泊二日で嫁と回ったのですが、その時に急坂やら石段の上り下りをしていましたら、左の膝がおかしくなってしまったんですよ。最後の方はまともに歩くことすらできず、嫁につかまりながら歩くと言う、なんとも情けない状態に。
そんな出来事があったため、石段とか上るのがちょっとした恐怖になっているんです。また膝の痛みが出てくるのではないかと…。
そんな事情がありますので、伊豆山神社の本宮への参拝はかなり不安です。
でもせっかくなので本宮まで行きたいです。僕は現在40代ですが、今登らなければもう登れなくなってしまうかもしれませんし。
したがって、覚悟を決めることに。
僕の自宅はマンションの9階なのですが、エレベーターを使わずに毎日階段で上り、伊豆山登山に備えます。
さらには膝のサポーターなるものを購入し、できるだけ膝に負担を掛けないようにもします。
万全の準備を整え、いざ旅行当日。
熱海駅に降り立ち、さっそくバスに乗り伊豆山神社に向かいます。
熱海駅では土産物屋や足湯の誘惑があったのですが、それは無事に伊豆山登山から戻ってからにすることにします。
バスに揺られ10分ほど。
伊豆山神社の入口に到着しました。
ご由緒
ご祭神は、伊豆山神と称される四柱で、火牟須比命(ほむすびのみこと)、天之忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)、栲幡千千姫命(たくはたちぢひめのみこと)、邇邇芸命(ににぎのみこと)です。
火牟須比命はカグツチとも称される火の神様、天之忍穂耳命は地神五代の2代目で、神武天皇の高祖父。栲幡千千姫命は織物の神様として信仰されている日本神話の女神で、安産や子宝の神様としても信仰されています。邇邇芸命(ににぎのみこと)は天孫降臨で地上に降りた神様です。
創建の詳しい年代などは不明ですが、社伝によると紀元前5世紀~紀元前4世紀の、第5代孝昭天皇の時代とされています。
かつては伊豆御宮、伊豆大権現、走湯大権現、走湯大権現、走湯社などと称され、その源は湧き出る霊湯である「走り湯」で、走湯大権現とは走り湯が神格化された呼び方です。
多くの仏教者や修験者が修行を積んだ霊場でもあり、空海が修行したと言う伝承もあります。天台宗や真言宗との関わりも深い神仏習合の神社でした。
また、源頼朝とも縁の深い神社で、彼が伊豆国に配流された際には、源氏再興を祈願した神社でもあります。後に妻になる北条政子と逢瀬の場でもありました。
頼朝が開いた鎌倉幕府、戦国時代には北条家、江戸時代には徳川家により厚く崇敬されます。
豊臣秀吉の小田原征伐の際には焼き討ちに遭い焼失しましたが、徳川家康により復興しています。
明治維新の神仏分離令により、現在の社名である伊豆山神社へと改称されました。
全国各地に点在する、伊豆山神社、伊豆神社、走湯神社の起源であり、総本社である神社です。
強運守護、福徳和合にご利益があるとされ、頼朝と政子の逸話などから、縁結びにもご利益があるとしても知られている神社です。
境内案内
熱海駅からバスに乗り「伊豆山神社前」のバス停で降りますと、目の前が伊豆山神社の入口です。

バス停のすぐ近くには伊豆山神社のご由緒がわかりやすく書かれていました。

バス停から上へと続く石段を上がると伊豆山神社なのですが、下へも延々と石段が続いています。下った先には「走り湯」という横穴式の源泉があるとのこと。余裕があったら後ほど行ってみることに。

下りの石段脇には布袋様の石像です。その先には熱海桜も咲いていました。

いざ、伊豆山神社へと向かいます。

伊豆山神社には梛(なぎ)の木が何本もあるようです。入口にもありました。

一礼して最初の石鳥居をくぐります。

石段を登ります。膝の不安を抱えながら。

二の鳥居に到着。

二の鳥居の右手に祖霊社がありましたので、立ち寄って手を合わせます。

一礼して二の鳥居をくぐり、再び石段を上がります。

途中右手には足立権現社。修験道の開祖とされている役小角(えんのおづの)が祀られています。足の病などのにご利益があるとされています。こちらにも参拝。

さらに少し上った先、左手に結明神社です。こちらにも参拝。ここからは海も見えて景色が良いです。結明神社の本社も、本宮に行く途中の山の中にあるようです。

長い石段を上り切った先に、開けた境内と社殿が姿を現しました。

参道の右手には社務所があります。本宮にも参拝した後に、こちらで御朱印を頂くことに。

社務所の手前には、御守りなどの案内とともに、「朱印帳はただいま品切れ中」と言う貼り紙も。嫁が伊豆山神社の御朱印帳が欲しいと言っていて購入予定だったのですが…残念。

参道に戻ります。左手に手水舎です。

手水舎には「赤白二龍」と呼ばれる紅白の龍がいます。赤は火を表し、白は水を表すと。こちらでお清めをします。

お清めを終え、拝殿へと向かいます。

数段の石段を上がると、狛犬さんがお出迎えです。こちらは左の狛犬さん。

こちらが右の狛犬さん。どちらも大きくはありませんが、凛としていますね。

左の狛犬さんの先には境内社が一つ。雷電社です。

雷電社の手前に光石があります。石の後ろにあるのが道祖神で、その道祖神(猿田彦大神)と共に地上に降り立った石だとか。ご利益があるようにと、触ったり座ったりしてみました。

再び参道に戻り、拝殿へと歩を進めます。

参道の左右は開けていて、左手には池もありました。

石段の先に拝殿です。赤を基調とした建物です。社殿の後ろは深い森になっています。

屋根の彫刻が目を惹きました。龍や獅子に交じって、麒麟らしき神獣や、鯉もいました。

参拝させて頂きます。

境内を散策してみることに。拝殿を背にして参道を見ますと、こんな景色です。右手の先には海が見えます。

こちらは拝殿の左側。広くなっています。そちらに行ってみます。

社殿を左斜め前のアングルで。赤い社殿が素敵です。

さらに奥に進みますと、「腰掛石」があります。ここに源頼朝と北条政子が腰掛け、愛を語らったと言われています。

腰掛石の奥は駐車場にもなっています。こちらの駐車場からですと、石段を登らずに済みますので、石段が厳しい方でも参拝できますね。駐車場の先に鳥居があるのですが、なんとそこには「小泉今日子」の名前が。小泉今日子さんが奉納した鳥居でした。

「小泉今日子鳥居」の近くからは海も見えます。境内から海が見える神社っていいですね。

境内には大きな木が何本もあります。どれも素敵です。

拝殿前の石垣にはご由緒が。

こちらは社殿に向かって右手です。大きな楠の存在感がすごいです。

右手も散策してみます。境内の案内図があり、この先僕たちが登ろうとしている本宮も載っています。

案内図の隣には大きな石碑がありました。何の石碑かはわかりませんでしたが…。

案内図を挟んで、反対側にも石碑です。大きな楠の脇にあります。

楠を見上げますと、その大きさに圧倒されます。大きな木は見ているだけで惹き込まれてしまいますね。

こちらは社殿を右斜め前から撮影。石垣越しですが。

社殿の右奥にも道が続いています。

その先には伊豆山郷土資料館。

郷土資料館の奥に鳥居があり、そちらが本宮へと向かう参道の入り口になっています。鳥居の脇には、これまた大きく立派な楠が聳え立っていました。もの凄くでかい木です。

一礼して鳥居をくぐります。鳥居の先にあるのが白山神社遥拝所です。本宮までの道中に白山社があるのですが、その遥拝所がこちらになります。

登山の安全を願い、遥拝所にも参拝します。そして、いざ本宮へ向けての登山に出発です。伊豆山神社本宮への参拝は、こちらの記事で紹介しています。
参拝を終えて
熱海に着いて、真っ先に向かった伊豆山神社。
熱海駅からはバスも一時間に4本ほど出ていましたし、とても行きやすい神社でした。乗車時間も10分かからずに神社の入口まで到着したかと思います。
バス停の目の前に鳥居がありますので、道に迷うこともありません。
僕たちが訪れたのは一月の中旬だったのですが、ちょうどバス停の下に熱海桜という早咲きの桜が咲いていまして、そちらも綺麗でした。うっかり写真に撮り忘れてしまったのですが。
バス停の目の前が伊豆山神社の鳥居で、その先には上へと登る石段が続いています。そしてその反対側、バス停から下にもず~っと長い石段が続いていいるんですよ。延々と下っています。一番下から登った場合、なんと全部で837段あるらしいです。恐ろしい…。
どうせなら一番下から登ってみたいという気持ちもないわけではないんですけどね。
この後に本宮への登山を控えていた僕たちは、下の石段はとりあえず見なかったことにして、まずは伊豆山神社に参拝することに。
バス停から上へと登る石段も短くはないのですが、めちゃめちゃ長いわけでもありません。途中には境内社もありますし、のんびり登ればそこまできつくないかと思います。
膝に不安を抱えている僕も、問題なく上がれました。
石段を上がり切った先には開けた景色が待っていて、上からは熱海の海を臨むこともできます。なかなか素敵な景色です。
赤を基調とした社殿も素敵ですし、屋根の彫刻も素晴らしいです。手水舎の赤白二龍、腰掛石、光石など、見どころも色々あります。小泉今日子の名前が書かれた鳥居も。小泉今日子さん、今はあれな感じになっちゃってますけど、鳥居の奉納をされていたんですね。
腰掛石は、源頼朝と北条政子が座っていたとのことですので、想いを馳せてみたり。
大きな楠が何本かあったのですが、どれも大きくて圧倒されました。
大木に触ってみたり、石を触ってみたり、海を見ながらのんびりしてみたり。
ゆったりとした時間を過ごすことができました。
この後はいよいよ、本殿の右奥の入口から山道に入り、険しい道のりが続くと言う、伊豆山神社の本宮社を目指すことに。気合いを入れて。
伊豆山神社の御朱印は、本宮参拝後に下山してから頂いたのですが、こちらの記事で先に紹介しておきます。
社務所では、赤白二龍が描かれた「強運ステッカー」も購入しました。災いや不幸を跳ね返し持ち主を守るというステッカーです。

ほんとは嫁が伊豆山神社の御朱印帳が欲しいと言っていたのですが、とても人気があるようで、残念ながら品切れだったんです。その代わりと言ってはなんですが、こちらの強運ステッカーを手に入れることに。
まだどこに貼るのか決めていませんが、かなり厚くて硬く、しっかりとしたステッカーです。良い場所を見つけて貼ろうと思います。
この後向かった本宮は、かなり険しい道のりだったのですが、こちらの伊豆山神社まででしたら、無理なくどなたでも参拝できるかと思います。
石段の上にも駐車場がありますので、車の場合には石段を登らずに参拝することもできます。
車でなくても、熱海駅からバスを使えば入口まで楽に来ることができます。
熱海観光の際には、ぜひ訪れてみてください。
御朱印
こちらが伊豆山神社の御朱印です。

御朱印の受付時間
御朱印と御守りを頂ける時間は、9時から16時までです。
(※お時間やご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)
アクセス
住所は静岡県熱海市伊豆山上野地708-1です。
伊豆山神社の公式サイトはこちらです。
https://izusanjinjya.jp/
電車
JR「熱海駅」からバスで7分。
熱海駅を出ると左手にバスターミナルがあります。4番バス乗り場(七尾、伊豆山循環)からの乗車です。
駐車場
参拝者用の駐車場があります。石段の上(社殿の奥)と下(バス停の近く)の両方に駐車場がありますので、石段を上るのが厳しい方は、上の駐車場を使うと便利です。
周辺のパワースポット
熱海市の神社一覧
僕が参拝した熱海市の神社一覧です。