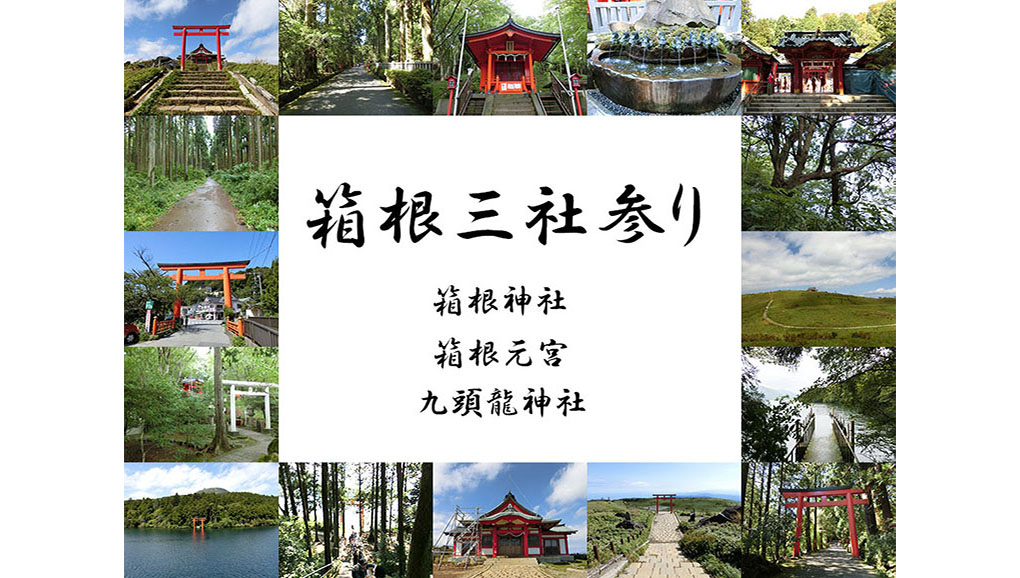調布市の初詣のご案内です。市内の各地域ごとに、初詣にお勧めの神社を一覧で紹介しています。
初詣は大きな神社に出掛けるという方も多いとは思いますが、ご自分の住んでいる地域を守ってくださっている神社(氏神さま、産土さま)に参拝することも大切です。
氏神さまに、前年を無事に過ごすことができた感謝をお伝えし、新年のご挨拶と平安の祈願をしましょう。
調布市の神社マップ
それでははじめに、調布市にある神社を地図で一覧にしていますので、参考にして頂ければと思います。
調布市内の比較的大きめな神社のみ掲載しています。
上記が調布市にある全ての神社ではありません。小さな神社や祠など、実際にはさらに多くが存在しています。
また、こちらの記事では一部を除き、基本的には神社のみの紹介で、寺院は紹介しておりませんので、ご了承ください。
次項より、調布市内の神社を、それぞれのエリアごとに、ざっくりな説明と併せて紹介していきます。
調布の初詣
布多天神社
飛鳥時代より以前に創建されたといわれている、大変歴史の古い神社です。江戸時代にはこの辺りは布田五宿と呼ばれ栄え、その総鎮守でもありました。元々は現在より多摩川寄りにありましたが、戦国時代の多摩川大氾濫により、現在の地に遷座しています。『ゲゲゲの鬼太郎』では、社殿の後ろに広がる森が、鬼太郎の棲み家として描かれています。調布駅から徒歩6~7分です。(調布市調布ヶ丘1-8-1)
下石原八幡神社
旧下石原宿の鎮守です。創建の年代は不明ですが、江戸時代以前です。三頭一組で舞う「三頭獅子舞」は市の指定文化財にもなっています。また、『ゲゲゲの鬼太郎』の猫娘が、こちらの社殿の軒下に住んでいる設定でも知られています。調布駅と西調布駅の中間辺りに位置しています。甲州街道沿いです。(調布市富士見町2-1-11)
若松稲荷神社
布多天神社の境外末社です。甲州街道沿いにある神社で、調布市立第一小学校の一区画にあります。元々は屋敷神だったお稲荷さんだといわれています。調布駅から徒歩5分です。(調布市小島町1-8-9)
上布田稲荷神社
ゲゲゲの鬼太郎モニュメントが並ぶ、天神通り商店街の中にある、小さな稲荷神社です。調布駅からですと徒歩3~4分です。(調布市布田1-35-2)
※上布田稲荷神社は、残念ながら令和元年に取り壊しが行われ、現存しない神社となっています。
白山宮神社
創建の年代や経緯などは不明ですが、江戸時代以前には建てられていた神社と推定されています。石川県の白山信仰に基づいた神社です。調布駅と布田駅の中間、南側にあります。(調布市布田5-32-4)
さくら稲荷神社
調布駅の北側、駅からすぐのビルが立ち並ぶ一角にある小さな神社です。創建の年代や詳しい経緯などは不明です。境内には可愛い狛犬がいます。(調布市布田1-45-2)
布田・國領・柴崎の初詣
國領神社
「千年乃藤」と呼ばれる藤の花で知られている神社です。かつて多摩川沿いに鎮座していた第六天社が元になっています。昭和37年に、神明社のあった現在の地に遷座し、二社を合わせてお祀りし、現在の國領神社となりました。最寄駅は布田駅で、甲州街道沿いです。(調布市国領町1-7-1)
虎狛神社
「こはくじんじゃ」と読みます。飛鳥時代より以前の創建と考えられている、大変歴史の古い神社です。本殿は江戸時代中期のもので、調布市では最古の建造物です。境内の大きなクロマツが有名でしたが、残念ながら平成8年に枯死しています。調布駅、布田駅、國領駅の北に位置しています。(調布市佐須町1-14-3)
柴崎稲荷神社
かつては天満宮山王稲荷合社と呼ばれていたそうです。創建の年代や経緯などは不明ですが、小田原北条氏より社地の寄進を受けたといわれています。柴崎駅の北に位置しています。(調布市柴崎2-11-4)
八剱神社
鎌倉幕府の家臣等がこの地域に移り住み開村した功績を称え、八名の刀を神宝として奉祀したことから、八剱神社と呼ばれるようになった神社です。柴崎駅が最寄駅になります。(調布菊野台3-42-1)
深大寺の初詣
深大寺
天台宗の寺院で、正式名称は浮岳山昌楽院深大寺(ふがくさんしょうらくいんじんだいじ)です。奈良時代に水神である深沙大王を安置して創建されたと伝えられています。明治に発見された銅造釈迦如来倚像は国宝にも指定されています。日本三大だるま市の一つ「深大寺だるま市」でも知られています。調布駅、つつじヶ丘駅、三鷹駅、吉祥寺駅からバスが出ています。(調布市深大寺元町5-15-1)
青渭神社
平安時代以前の創建と伝えられている、深大寺町の総鎮守です。水神様である青渭大神を祀っていて、かつては境内に湧水の湧く大きな池があり、青波天神社とも呼ばれていました。御神木の大ケヤキでも知られています。神代植物公園や、深大寺のすぐ近くです。(調布市深大寺元町5-17-10)
諏訪神社
創建の年代などは不明ですが、かつては諏訪明神祠と呼ばれていたそうです。明治には稲荷神社と御嶽神社を合祀しています。調布駅、布田駅、國領駅などの京王線と、中央線の三鷹駅の中間辺りに位置しています。(調布市深大寺東町8-1-3)
又住稲荷神社(深大寺稲荷神社)
又住と呼ばれていたこの辺りの地区の鎮守社です。深大寺元町にある稲荷神社のため、深大寺稲荷神社と呼ばれることもあります。創建の年代や経緯は不明です。調布駅、布田駅が最寄駅で、虎狛神社の少し北に位置しています。(調布市深大寺元町2-3-14)
富士嶽浅間神社
明治14年の創建です。富士嶽浅間神社教会が設立され、その際に社地が提供され、創建された神社です。神代植物公園の北にあり、調布駅、三鷹駅、武蔵境駅の中間辺りになります。(調布市深大寺北町1-38-3)
池ノ上神社
絵堂と呼ばれていたこの辺りの地区の鎮守社です。創建の年代や経緯などは不明です。明治40年には稲荷神社を合祀しています。深大寺の少し南、中央高速のすぐ近くにある神社です。(調布市深大寺南町4-2-9)
宿神明社
宿と呼ばれていたこの辺りの地区の鎮守社です。創建の年代や経緯は不明です。天照皇大神(あまてらすおおみかみ)を祀る神社です。神代植物公園の西にあります。(調布市深大寺元町5-32-2)
つつじヶ丘・仙川の初詣
金子厳島神社
旧金子村の鎮守です。かつては辨財天稲荷合社と呼ばれていて、境内には池があったそうです。最寄駅はつつじヶ丘駅です。柴崎駅からも徒歩圏内です。(調布市西つつじヶ丘1-15-8)
仙川八幡神社
創建の年代や経緯は不明ですが、江戸時代には、旧下仙川村と旧北野村の鎮守社だった神社です。大正時代には、下仙川にあった巌嶋社と代官田神社を合祀しています。最寄駅は仙川駅です。(調布市緑ヶ丘2-5-5)
糟嶺神社
「かすみねじんじゃ」と読みます。旧入間村の鎮守です。多摩群には墳陵(墳墓)が4ヶ所あり、そのうちの一つといわれる上に鎮座しています。つつじヶ丘駅と喜多見駅の中間辺りに位置しています。國領神社の兼務社です。(調布市入間町2-19-13)
田中稲荷神社
創建の年代や経緯は不明です。元々は新井一族の氏神だったことから、現在も新井稲荷とも呼ばれている小さな神社です。國領神社の兼務社です。つつじヶ丘駅、仙川駅の南にあります。(調布市若葉町3-12-6)
西調布・飛田給の初詣
上石原若宮八幡神社
第16代天皇である仁徳天皇を祀っています。旧上石原宿の鎮守社で、新撰組の近藤勇とも縁のある神社です。江戸時代後期に再建された本殿は総けやき造りで、精巧な彫刻も施されています。境内は「はけの緑」と呼ばれる鎮守の森になっています。西調布駅が最寄駅です。(調布市下石原3-5-2)
道生神社
飛田神社と道生神社、二つの神社が合祀され、祀られています。それぞれ元は、稲荷神社、山王社と称されていました。明治17年に合祀されています。現在の調布飛行場の地に鎮座していましたが、昭和18年に飛行場建設に伴い、現在の地に遷座しています。飛田給駅のすぐ東にあります。(調布市飛田給2-39-20)
金山彦神社
鉄や刃の神様である金山彦命が祀られています。江戸時代の初期に、刀鍛冶により創建されたといわれています。鉄など金属を扱う仕事の方から、特に信仰の厚い神社です。西調布駅から徒歩7~8分です。(調布市下石原1-41)
隣接地域の神社
お住まいの地域によっては、調布市と隣接する・世田谷区・三鷹市・府中市・小金井市・狛江市・稲城市・川崎市多摩区の神社の方が行きやすい場合もあるかと思います。
周辺地域の初詣にお勧めの神社についても、下記にそれぞれリンク記事を貼っておきましたので、是非チェックしてみてください。
・川崎市多摩区(未作成)