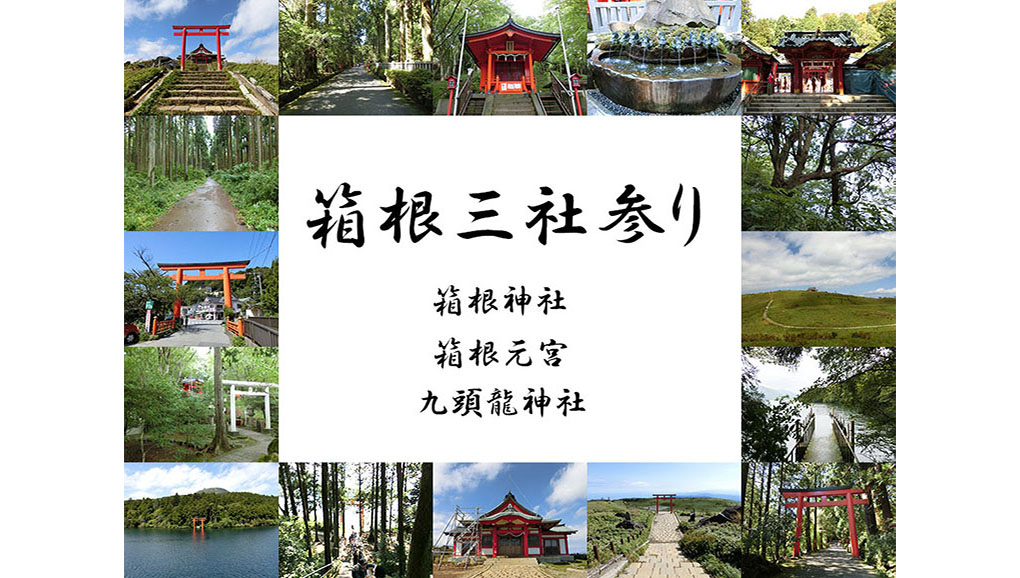高千穂町の三田井にある逢初天神社の参拝レポートです。
読み方は「あいそめてんじんじゃ」です。瓊々杵命は、井川(逢初川)に映った木花開耶姫に一目惚れをし、川のほとりで求婚したといわれていて、その井川が流れる地に鎮座している神社です。縁結びのご利益でも知られています。
序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。
高千穂の「逢初天神社」へ
こちらの逢初天神社は、その社名も素敵ですけれど、日本神話の世界に直接繋がっているという、高千穂ならではの場所の一つでもあります。
4月の中旬、4泊5日というガッツリな日程で、嫁と二人高千穂にやって来まして、この日はその2日目。
ここまでも日本神話に所縁のある場所に、何か所も足を運びました。
天照大神がお隠れになった天岩戸や、八百万の神々が集まり相談をした天安河原、日向三代の宮ともいわれる高千穂神社など、有名どころはもちろん、他にも天照大神の宮居跡といわれる天岩戸神社東本宮や、山幸彦の宮居跡といわれる祖母嶽神社など、素敵な場所を巡らせて頂きました。
神話の中で登場した世界とリンクした場所を、自分が実際に見たり歩いたりできるというのは、不思議な感じもしますし、とっても楽しいです。神社好きとしてはたまらない時間です。
そしてこちらの逢初天神社は、天孫降臨の瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)と、その妻である木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)、この夫婦の言い伝えが残る神社とのこと。どうやら二人の出会いや求婚に深く関わりのある神社のようです。
まさに縁結びの神社ですね。
そんな神社に僕たち夫婦も、仲良く揃って参拝できるというのは、幸せなことでもあります。
この日は早朝から神社巡りをしておりまして、次に向かう逢初天神社は11か所目の神社です。既に二桁いってます。
時間は14時過ぎくらいでして、逢初天神社も含め、あと4ヵ所の神社に足を運んでから、ホテルに戻る予定です。
10か所目に訪れた石神神社より、車を走らせること15分ほど。
地図を確認しつつ、細い道に入り進んで行きますと、右手に高い木々が茂る一角が現れ、その入口には鳥居がありました。
逢初天神社に到着です。
ご由緒
ご祭神は、事勝国勝長狭神(ことかつくにかつながさのかみ)、木花開耶姫(このはなさくやひめ)、森天神(もりてんじん)、中園天神(なかぞのてんじん)、逢初川(あいそめがわ)です。
事勝国勝長狭神は、知恵を授ける神、予言の神である塩土老翁(しおつちのおじ)の別名です。木花開耶姫は、天孫降臨の瓊々杵命の妻です。
創建の年代や経緯は不明ですが、境内には、江戸時代後期の天保の時代に社殿が造営されたとの案内書きがあります。かつては逢初天神宮と称されていて、現在よりも低い場所に鎮座し、その跡地が残されています。旧社殿は昭和21年に台風により崩壊してしまい、その後現在の場所に遷座しています。
瓊々杵命が、この地を流れている井川(逢初川)に映った木花開耶姫に一目惚れをし、川のほとりで求婚したといわれていて、その井川が流れる地に鎮座している神社です。
逢初川は現在も境内を流れています。
瓊々杵命と木花開耶姫の出会いに因み、縁結びのご利益でも知られています。
境内案内
こちらが逢初天神社の入口です。木の鳥居に七五三の注連縄が掛けられています。

鳥居の右手前には、逢初川と神社のご由緒書きと、ピンクのシャクナゲ。

反対側、鳥居の脇には川があり、これが逢初川かと思われます。水は流れていませんでした。その向こうにも社が見えましたので、後ほど行ってみます。

一礼して鳥居をくぐります。ガラスのある珍しい扁額です。

参道にもシャクナゲが咲いています。

シャクナゲと杉の参道を上がります。そこそこ勾配があります。

左手、大きな杉の木立の中に祠のようなものが見えました。どうやら先ほどの鳥居の左手から行けそうですので、後ほどそちらにも行ってみることに。

参道の脇にも、シャクナゲに隠れるように、石祠が二つ。

右手に少し開けた場所があるようなので、ちょいと寄り道してみます。

杉の向こうは、長閑な山の景色でした。桜も咲いています。

こちらにはトイレもありました。

参道に戻ります。参道は左にカーブして延びています。

前方に社殿が見えてきました。

社殿は白を基調とした建物です。周囲には杉が連なっています。

右には変わった形の手水石。

少し引きの絵で、社殿を正面から。

扉が開けられましたので、少し開いて参拝させて頂きます。

社殿を振り返りますと、こんな感じです。僕たちはこの右手の方から来たのですが、どうやら社殿へと真っ直ぐ延びている別の参道があったようですので、そちらにも下りてみることに。

石段を下りた先には、別の鳥居がありました。一礼していったん境外へ出て、撮影。

再び鳥居をくぐり、境内へ。この正面の参道からですと、こんな感じで社殿が見えてきます。

右手にはツツジが綺麗に咲いています。

左には並ぶ石碑。

再び社殿の周囲を散策。こちらは社殿を右斜め前から。

社殿の奥は杉の森です。

散策を終え、元来た参道を戻ります。

境外へ出て、鳥居に向かい左手を散策してみます。こちらは逢初川をお祀りした祠かと思われます。

さらに奥にも、少し大きな社です。

こちらではお水がお祀りされているようです。

そして少し山の方に上がると、注連縄が掛けられた祠のような、灯籠のようなものが一つ。逢初天神宮の跡地との案内書きがありました。こちらにも参拝させて頂き、逢初天神社を後にします。

参拝を終えて
入口の鳥居の脇には、水は流れていませんでしたが川がありまして、おそらくそれが逢初川だと思います。
かつて瓊瓊杵尊は、この川に映った木花開耶姫に一目惚れをし、この川のほとりで求婚したと、そう言い伝えられているそうです。
古事記では瓊瓊杵尊は、笠狭御前(かささのみさき・現在の鹿児島県にある野間岬)で木花開耶姫に出会ったとされていますが、日向三代が暮らしていたとされるこの高千穂にて、出会っていてもおかしくないですからね。
それに、川面に映った木花開耶姫を見て、瓊瓊杵尊が一目惚れしたというのも、また素敵なお話ですし。
川に水は流れていませんでしたが、素敵な言い伝えのある川を見ることができましたし、奥にあったお水がお祀りされた社にも参拝できました。
境内ではシャクナゲやツツジ、さらには桜も咲いていまして、木花開耶姫をお祀りした神社にて、綺麗な花を見られるというのも、またいいものだな~と。
こちらの逢初天神社は、参道が二つあったのですが、それぞれに違った景色が楽しめました。
最初にくぐった木の鳥居は、扁額がとっても変わっていまして、縦長なうえにガラスがはめ込まれていました。ガラスのある扁額というのは、僕は初めての出会いです。
また、高千穂では手水石が変わった形の神社が多く、こちらも独特の形でした。おそらく石ありきで、石そのものの形が生かされた手水石なんだと思います。ゆえに、それぞれ特徴のあるもので、二つとない形状のものなのではないかと。
変わっているといえば、かつての逢初天神宮跡地にあった、注連縄の掛けられた石灯籠のようなものも、他ではなかなか見ないもので、ちょっと不思議でした。
冒頭で書いたことと重複はしてしまいますが、瓊瓊杵尊と木花開耶姫の言い伝えが残る神社に、こうして夫婦そろって参拝できるというのは、なんとも幸せなことです。
逢初天神社、参拝できてよかったです。
続いては、槵觸神社へと向かいます。
御朱印
逢初天神社の御朱印はありません。
(※ご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)
アクセス
住所は宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井6250です。
逢初天神社の公式サイトはありません。
駐車場
入口のご由緒書きの前に、1台でしたら駐車できます。

トイレ
参道の途中、右にあります。

周辺のパワースポット
高千穂の神社巡り
高千穂の神社マップや神社巡りについては、こちらの記事でまとめてあります。
高千穂町の神社一覧
著者が参拝した高千穂町の神社の一覧です。