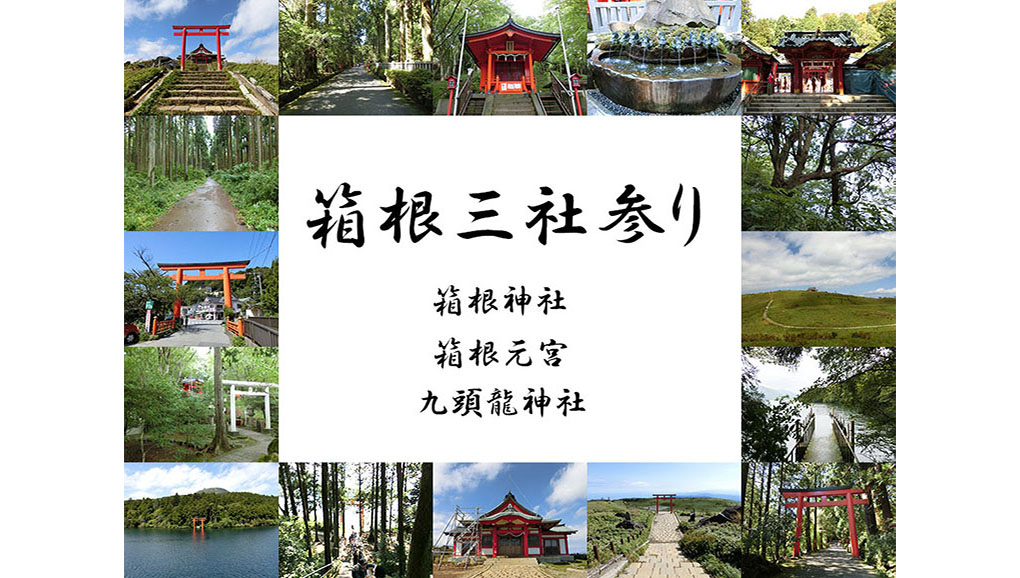三浦市の城ヶ島にある楫の三郎山神社の参拝レポートです。
読み方は「かじのさぶろうやまじんじゃ」です。楫ノ神社、楫の三郎神社とも称されています。城ヶ島バス停のすぐ近くにあり、大蛇伝説もある「楫の三郎山」の頂上に鎮座していて、漁業関係者からも信仰の厚い神社です。
序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。
城ヶ島の「楫の三郎山神社」へ
楫の三郎山神社、変わった名前の神社ですよね。三郎さんに縁のある神社では?と推測することはできますけれど。
僕はアホなので「楫」が読めなかったのですが、「かじ」と読むんですね。船の舵(かじ)だったり、舟を漕ぐ櫂(かい)などを指すようです。
この日は嫁と二人で訪れた、三浦海岸への一泊二日の小旅行、二日目です。
前日は浦賀周辺の神社巡りを中心に歩き回りました。お昼には美味しい魚も食べました。
夕方には宿をとっていた城ヶ島に移動し、「城ヶ島京急ホテル」に一泊。
僕たちは二年前にも三浦海岸を旅行し、同じホテルに宿泊しています。城ヶ島の海岸が目の前に広がるという素敵な場所で、お値段の方も高くはなく、お勧めなホテルです。
今回は9月の半ばで完全なシーズンオフだったようで、大きなお風呂も貸切状態でした。嬉しいような申し訳ないような。
どうやら夏休みが終わり、その後10月からは修学旅行で混むらしいのですが、9月半ばはちょうどその隙間のようで、かなり空いてるっぽいです。
お部屋もおそらく一番眺めが良いのでは?と思われるお部屋を用意して頂きました。部屋の大きな窓からは、城ヶ島の海が一望できる景色なんです。ありがたいです。
ご飯も美味しかったですし、お風呂もでかくて気持ち良かったですし、ゆっくりと疲れを取ることができました。
ほぼ貸切状態のホテルで一晩のんびり過ごし、翌日は朝から城ヶ島を散策してみます。
二年前は7月の終わりに来まして、あまりの暑さに島の散策は断念したんですよ。晴天で、陽射しが容赦なく照りつけていて、こりゃ熱中症になりそうだから、とやめた覚えがあります。
ですのでがっつりと島を歩くのは、二度目にして今回が初めて。
前日は曇り空だったのですが、この日は朝から気持ちの良い晴れ。陽射しも強いです。
しかし夏のピークは過ぎていますので、暑さもなんとか大丈夫そう。
散策に出掛けることにします。
晴れ渡る空と城ヶ島の海岸の絶景は、ほんとに素晴らしいです。

城ヶ島京急ホテルより、眺めの良い海岸沿いを20~30分ほどてくてくと歩きますと、城ヶ島の名所でもありパワースポットでもある「馬の背洞門」に到着します。

ここがまた素晴らしかったです。
岩の間から海を見ていると、なんだか不思議な気持ちになってきます。
いつまでもいたくなるような場所でした。
そこそこの距離は歩かないと辿り着けない場所ではあるのですが、歩くのが大丈夫でしたら是非行ってみてください。
馬の背洞門については、僕が別で書いているこちらのブログでも詳しく書いています。
とにかく絶景でした。
城ヶ島の大自然を堪能した後は、預けていた荷物を取りにいったんホテルに戻り、城ヶ島から三崎港へと向かうバス乗り場へと向います。
そして、この記事で紹介する「楫の三郎山神社」は、そのバス停のすぐ近くにあるんです。
二年前に城ヶ島を訪れた際には、着いてすぐ、バスを降りてまず楫の三郎山神社に参拝しました。なんか山があるから行ってみよう、というノリで、行ってみたら神社があったんです。
今回もほんとは前日に行きたかったのですが、城ヶ島に到着するのがかなり遅い時間になってしまい、暗くなりかけていましたので、翌日にしました。帰り道に寄ろうと。
バス停から少し海の方に歩きますと、こんもりとした小さな山があります。
その山の頂上が、楫の三郎山神社です。
ご由緒
ご祭神は、対岸の三崎にある海南神社のご祭神、藤原資盈(ふじわらのすけみつ)公の家臣である、三郎(さぶろう)という人物です。
創建は平安時代前期の貞観8年です。皇位継承争いに絡んで左遷された藤原資盈が、筑紫国(現在の福岡県辺り)に赴く途中、暴風雨に遭い漂流した末、三崎に着岸しました。このときに船の舵取りを司っていた家臣である三郎を山に祀り、以来その山が三郎山と呼ばれるようになったそうです。
また、藤原資盈に「我が住むべき地があるか」と問われた三郎が、梶(楫)でそれを占い、梶が落ちた山に祠が建てられ、そこが「楫の三郎山」と呼ばれるようになったとの説もあります。
大正時代の初期頃までは、山には主の大蛇が住んでいて、登ると祟りがあるとの言い伝えがあり、誰一人登ったことがなかったそうです。
対岸の海南神社とも関わりの深い神社で、現在は、航海の安全と大漁を祈願する漁業関係者からの信仰が厚い神社です。
境内案内
城ヶ島のバス停から海の方を見ますとお食事処があり、その後ろに山があります。その山が「楫の三郎山」です。

お食事処の脇を抜け、三郎山へ向かいます。前方は海。

三郎山にはバス停から2分ほどで到着です。大きな山ではありませんが、海の波や風によって浸食されたと思われる岩肌が目を惹きます。

少し先には三郎神社の鳥居です。ここから楫の三郎山に登ることができます。この景色、好きです。

鳥居の脇には楫の三郎山神社のご由緒。大蛇が住んでいるとの言い伝えが書かれていて、少しビビります。

一礼して鳥居をくぐり、三郎山に足を踏み入れます。

石段を上ります。海風が心地良いです。

すぐに山頂に到着です。鳥居と赤い幟旗があるのが目に入ります。

振り返るとこんな感じです。最高です。

来て良かった。

しばらく海を眺めてから、鳥居に向かいます。

鳥居の手前には手水鉢。水がありませんでしたので、手をはたいてお清めをします。

鳥居の前に立ちます。赤い旗には「大漁祈願」や「学業祈願」が書かれていました。

海からの静かな風に吹かれながら、参拝します。

参拝後、祠の左奥に小路が続いていましたので、行ってみます。

小路がどこに続いているのかちょっとワクワクだったのですが、行き止まりでした。しかし、そこからの眺めがこれまた素晴らしかったです。

祠の前に戻ります。そして海を見ながらしばらくボケ~っと。

祠を背にしますと、こんな景色です。対岸に見えるのが三崎港です。

さらにしばらくボケ~っと海を眺めてから下山し、楫の三郎山神社を後にしました。

参拝を終えて
晴れ渡る空の下、城ヶ島の美しい海岸と、遠くまで見渡せる海。
楫の三郎山からの景色が、とっても気持ち良くて最高でした。城ヶ島に行きましたら、ぜひとも三郎山は登ってみてください。お勧めです。
山と言っても、入口から頂上までは1分くらいで登れてしまいますし、特に険しい道のりでもありません。
僕たちは二年前にも訪れているのですが、その時も景色が素晴らしく、気持ち良かったのを覚えていましたので、少し懐かしい気持ちにもなりました。
ただ二年前は7月末の夏真っ盛りだったためか、山にはフナムシやらムカデやら、色んな虫がそこら中を這い回っていまして、虫の苦手な嫁が忙しく悲鳴を上げていてうるさかったんですけどね。
今回は9月半ばで、そこまで虫を見かけることもなかったです。僕としては少し寂しい気持ちもありましたけれど。
昔は大蛇がいると怖れられていたそうですが、確かに大蛇がいてもおかしくなさそうな雰囲気もある場所です。実際に大蛇に出くわしたら怖いですけれど、想像するとちょっと神秘的な感じもして、山の魅力が増しますね。
朝から陽射しも強く、まだまだ暑さは残る時期ではありましたが、山の上には心地よい海からの風が吹いていました。
ついつい、のんびりと長居したくなってしまう場所です。
僕と嫁以外には人の気配も全くなく、山からの素晴らしい景色を独占させて頂きました。
神社の回りには、「大漁祈願」と書かれた赤い旗も掛けられ、地元の漁師さんなどから厚く信仰されていることが窺えます。
入口には神社のご由緒が書かれているのですが、やっぱり社名の通り、「三郎」さんに関係のある神社なんですね。当たり前かもしれないですけど。
僕たちはこの後、対岸の三崎にある海南神社に向う予定だったのですが、三郎さんはその海南神社のご祭神、藤原資盈さんの家臣だった人物とのこと。
三浦に流れ着いた藤原資盈さんですが、その後は海賊を平定したり、福祉に努めたりして、人々から崇敬され、亡くなった後にはご祭神として祀られ、それが海南神社になったそうです。
僕たちは、楫の三郎山神社と海南神社が関係があるとは知りませんでしたので、どちらにもこの日参拝できるというのは嬉しい偶然です。
素晴らしい海岸の景色に名残惜しさを抱きつつ、楫の三郎山神社を後にした僕たちは、三崎港へと向うバス停へ。
城ヶ島には前日の夕方からこの日の午前中まで、そんなに長居はできなかったのですが、馬の背洞門、そしてこの楫の三郎山神社と、気持ちの良い二ヶ所に立ち寄ることができて、大満足です。
城ヶ島京急ホテルも良かったですし、城ヶ島にはまたいつか来ようと思います。
バスに乗り城ヶ島を出て、三崎港へと到着した僕たちは、その足で「海南神社」へと向います。
御朱印
楫の三郎山神社では御朱印は扱っていません。
(※ご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)
アクセス
住所は神奈川県三浦市三崎町城ケ島670です。
楫の三郎山神社の公式サイトはありません。
電車
京浜急行「三崎口駅」からバスで約30分。
2番乗り場より「城ヶ島行き」に乗り30分ほどです。終点の「城ヶ島」で下車し、バス停からは徒歩すぐです。
駐車場
バス停の近くに駐車場があります。
周辺のパワースポット