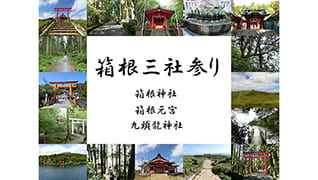茅野市にある葛井神社の参拝レポートです。
読み方は「くずいじんじゃ」です。諏訪大社上社の末社であり、上社の年中神事の最後を飾る「御手幣送りの神事」が毎年行われている神社です。境内の「葛井の清池」には不思議な伝説もあります。茅野駅から車で7~8分です。
序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。
葛井の清池がある「葛井神社」へ
僕は生まれも育ちも、この葛井神社のある茅野市です。現在は東京在住ですが、二十歳前くらいまではずっと茅野にいました。現在も実家は茅野にあります。
しかしながら、葛井神社の存在は今まで全く知りませんでした。全く知りませんので、当然一度も訪れたことはありません。
きっかけは今年の5月。実家に帰省した際に、嫁と一緒に諏訪大社の上社に参拝しました。
僕はこのようなブログを書いているにも関わらず、いまだに地元にある諏訪大社の御朱印を頂いたことがなかったので、機会を作って参拝した形です。
小さい頃から何度となく訪れていた神社ですが、境内をのんびり散策したり、御朱印を頂いたのはその時が初めてです。
諏訪大社は、全国に一万社以上あると言われる諏訪神社の総本社で、諏訪湖の南が上社、北が下社となっています。上社には前宮と本宮、下社には秋宮と春宮があり、この四つの宮の総称が諏訪大社です。
まずは5月に上社の前宮と本宮に参拝し、その記事をこのブログに書くにあたり、諏訪大社について色々と調べていたわけです。
その過程で存在を知ったのが、この葛井神社なんです。
葛井神社には「葛井の清池」と言う池があり、これをGoogleで画像検索したところ、なんとも神秘的な池の写真が現れました。
これは行ってみたい、是非この目で見てみたい、思わずそう思ってしまう景色です。
そんな場所に、こんな神秘的な場所があったのかと。
地図で場所を検索すると、茅野駅からもそう遠くなく、僕の実家からでも車ですぐに行ける距離です。
葛井神社についての予備知識を得た僕は、次に実家に帰省した際に、足を延ばしてみることに決めました。
そして今年の8月。お盆よりも少し前です。
5月に回り切れなかった、下社の秋宮と春宮に参拝し、その帰り道に上社と関わりの深い神長官守矢史料館にも立ち寄り、最後に葛井神社を目指すことに。
守矢史料館を出て、カーナビに葛井神社の住所を入れ、車を走らせます。
そして走ること5分ほど。目的地付近には木が生い茂る一角があり、そこが葛井神社でした。
無事到着です。
ご由緒
ご祭神は、水の神様である槻井泉神(つきいずみのかみ)です。
創建の年代は不明ですが、古くから諏訪大社の末社であり、前宮とは関わりの深い神社です。「葛井」は久頭井、楠井、久須井、槻井などとも書かれます。
境内には神池である「葛井の清池」があり、元々は社殿もなく池そのものが御神体とされていました。社殿が建立されたのは明治以降になります。
毎年大晦日には、諏訪大社上社の年中神事の最後を飾る「御手幣送りの神事」が行われます。これは一年神事で手向けられた供物である幣帛や、榊や柳の枝、柏の葉などを御宝殿より取り下げ、葛井神社に運び、寅の刻(午前4時ころ)に葛井の池に投げ入れる神事です。すると卯の刻(午前6時ころ)には遠州(静岡県)にある「さなぎの池」に浮かび上がると伝えられていて、これは諏訪大社上社の七不思議の一つと言われています。
他にも葛井の清池には抜け穴伝説があり、同じ茅野市の多留姫神社(たるひめじんじゃ)にある「多留姫の滝」に流したものが、葛井の池に浮かぶとも言われています。
また、池には片目の魚が住んでいるとも、池にいる魚は全て片目だとも言われています。
境内には樹齢700~800年の大きなケヤキの古株もあります。
古くから諏訪大社と密接な関係があり、不思議な伝説のある神池を有する神社です。
境内案内
車を停めた駐車場のすぐ後ろが、社殿の裏側にあたる池だったので、入口の鳥居を探します。きちんと鳥居をくぐって境内に入りたいですからね。なかなか見つけられなかったのですが、坂の上に発見。ぐるっと坂の上に回り、鳥居の正面に立ちます。こちらが葛井神社の入口です。

鳥居の近くには庚申塚もありました。手を合わせます。

一礼して鳥居をくぐり境内へ。下り坂になっている参道を進みます。

参道の右手には「津島牛頭天王」と刻まれた石碑です。

参道は右に折れ、その先に社殿が見えます。

社殿の周りには、四隅にそれぞれ一本ずつ、御柱が立てられています。

社殿とちょうど向かい合うような位置に、大きな木の古株があるのが目に入ります。

古株に近付いてみます。樹齢700~800年と言われる大きな欅(けやき)の古株で、葛井神社の御神木です。上には屋根が載せられ、社のようになって祀られています。

ケヤキの正面に立ってみます。とても大きな株です。再三の落雷などにより危険な状態になり、昭和49年に現在の高さで切り落とされたとのこと。切られる前までは、大木が天に向かって聳えていたんだろうな~と。その姿も見てみたかったです。

ケヤキの前には説明が書かれています。「葛井神社千本欅」と呼ばれているんですね。

千本欅の後ろにも、大きな木が茂っています。

千本欅を振り返ると、葛井神社の拝殿です。

社殿はかなり古いもののように見えます。

静かな空気の中、参拝します。

拝殿の右手前には、葛井神社のご由緒が書かれています。

参拝を終え、境内を散策してみます。こちらは社殿を左斜め前から撮影。後ろには池があるのが見えます。

こちらは社殿の右手前に立っている御柱です。

社殿の右手から、後ろにある「葛井の清池」に向かいます。

池の入口には木で作られた鳥居です。空気が少し張り詰めています。

大きな池ではありませんが、この場所は神秘的な空気に包まれている感じがします。

池には鯉が何匹も泳いでいるのが見えました。この中に片目の鯉がいるのでしょうか。

葛井の清池をぐるっと回ってみます。こちらは後ろからの絵になります。池の周囲でしばしの時間を過ごし、葛井神社を後にしました。

参拝を終えて
念願の葛井神社にようやく参拝することができました。
僕の実家の近くに、こんなに神秘的で素敵な場所があったとは…。
余談ですが、この葛井神社のお隣にはアクアランドと言う施設があり、そこには屋内プールがあるのですが、僕の母親は週一でそのプールに泳ぎに行ってるみたいです。それだけ身近な場所ってことなんですけどね。
訪れたのはお盆前、8月の夕暮れだったのですが、時間帯のせいなのか、境内には始終僕と嫁の二人だけ。夏の夕暮れ時、静かな時間を独占させて頂きました。
葛井神社の大きな見どころは二つあります。
まず、なんと言っても僕が今回訪れた目的でもある「葛井の清池」です。
社殿のちょうど裏手に池があるのですが、池の周囲は少し空気が張り詰めている感じがして、独特の雰囲気がありました。大きな池ではありませんが、神秘的な景色が印象に残ります。
この池に投げ入れたものが、静岡にある「さなぎの池」に浮かぶと言う伝説がありますので、池の底から抜け穴があり繋がっているのかな~と。そんな想像をするとワクワクしてしまいます。
ちなみに「さなぎの池」は、「佐奈岐池」と書くようなのですが、場所がどこなのか判明していないそうです。静岡県の御前崎にある「桜ヶ池」ではないかと言う説もあります。桜ヶ池を画像検索したところ、龍神伝説もある不思議な池のようで、そちらにも行ってみたくなりました。
また、葛井の清池は同じ茅野市内にある「多留姫の滝」と繋がっているとも言われていますので、次回帰省した際には、多留姫の滝にも行ってみようと思います。
葛井の清池にいる魚は、全て片目だとも、片目の主がいるとも言われています。鯉が泳いでいるのが見えたので、できるだけ近付いて観察してみたのですが、残念ながら泳いでいた鯉が片目なのかどうかはわかりませんでした。
葛井の清池が神秘的で魅力的なので、ついつい池の印象で終わってしまいがちではありますが…。
もう一つ、境内には目を惹くものがありした。
それが千本欅です。
残念ながら昭和49年に切り落とされてしまった欅なのですが、この古株が巨大で、さぞかし大きな木だったんだろうな~と。当時の景色も知りたくなってしまいますね。
株の上には屋根が付けられ、社のようになっていたのも印象的でした。
欅と向かい合うように社殿があり、その後ろに池があります。欅、社殿、池が一つのラインになっていて、社殿と池を囲むように、四方には御柱が立てられています。
境内が全体的に神域のような雰囲気のある神社でした。
葛井神社は諏訪大社上社の末社ですが、諏訪大社に関連した場所は、魅力的なところがたくさんありますね。
気になる場所を全部回ったら、いつかそれらをまとめてみたいと思っています。
葛井の清池と千本欅のある葛井神社、参拝できて良かったです。
御朱印
葛井神社では御朱印は扱っていません。
(※ご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)
アクセス
住所は長野県茅野市ちの414です。
葛井神社の公式サイトはありません。
電車
JR「茅野駅」からタクシーで6~9分。
徒歩でも行けない距離ではありませんが、40分くらい掛かると思いますので、あまりお勧めはできません。
駐車場
10台ほど停められる駐車場があります。特別な日でない限りは問題なく駐車できるかと思います。諏訪ICからは10分ほどの距離です。
周辺のパワースポット