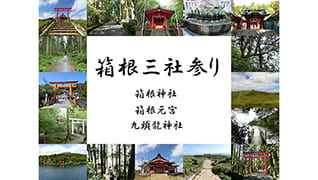高千穂町の押方にある二上神社の参拝レポートです。
読み方は「ふたがみじんじゃ」です。霊峰と崇められ、天孫降臨の山ともいわれる二上山を御神体とする神社です。二上山は男岳と女岳の二つが一つになっている山で、女岳の三合目付近に鎮座しています。現在の境内は、伊弉諾尊と伊弉冊尊による神生みの場所ともいわれています。
序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。
高千穂の「二上神社」へ
4月の中旬、嫁と二人で4泊5日という日程で高千穂旅行にやって来ました。
二上神社は、その3日目に訪れた神社になります。
神社巡りが中心の旅行でして、初日から行きたかった神社を片っ端からアホみたいに回り、2日目の終了時点で既に20社を超える数に足を運んだことに。
基本はレンタカーで回っていたのですが、3日目の午前中のみ、諸事情によりタクシーをチャーターしました。神和交通というタクシー会社さんで、3時間半のコースで好きな神社を巡ってくれるというのがありましたので、そちらでお願いしちゃいました。
元々タクシーで予定していたのが、秋元神社、黒仁田神社、向山神社の三社です。いずれもけっこうな山奥でして、どれくらい時間を要するのか読めない部分もあったのですが、もし時間が余りそうなら、他の神社もお願いしようと思っておりました。
結果、三社を回った時点で、残りは1時間と少し。
ですので運転手さんとも相談の上、翌日行こうと考えていた、二上神社に行ってもらうことにしました。
二上神社も事前に調べたところ、けっこうな山奥にある神社のようです。
高千穂には天孫降臨の地ではないかと考えられている地がいくつかあり、二上神社が御神体としている二上山もその一つです。他には、槵觸神社のある槵觸峰、宮崎と熊本と大分にまたがる祖母山、秋元神社の南に位置している諸塚山などですね。槵觸神社は一時期、二上神社と称されていたこともあるそうです。
高千穂はどこも素晴らしい山ばかりですので、瓊々杵尊がどこに降り立っていてもおかしくないと思ってしまいます。
どこが本当の天孫降臨の場所なのかなど、わかろうはずもありませんが、神話の世界のお話が、こうして現実の今と繋がっているということだけでも、凄いことだと思います。日本神話に所縁のある地を実際に歩けるというだけで、ワクワクしてしまいます。
二上神社へは、この日三か所目に訪れた向山神社からですと、いったん高千穂神社などのある街の方に少し戻ってから、向かう形です。
街だった景色は一瞬でまた山の中へと変わり、細い山道を進んで行きます。
そして集落があるエリアを抜け、坂を上って行きますと、目の前に突然鳥居が現れました。
二上神社に到着です。
ご由緒
ご祭神は、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と伊弉冊尊(いざなみのみこと)です。
伊弉諾尊と伊弉冊尊は、多くの国を生み、神を生んだ神様で、二神は兄妹でもあり夫婦でもあります。伊邪那岐命、伊邪那美命とも表記されます。
創建は平安時代の前期である昌泰の時代になります。古来より二上山の山中に二上大明神の祭祀場がありましたが、山が深く冬は雪が多く参拝が難しかったため、東と西の山麓に降ろして祀ることとなり、昌泰元年に創建されました。
東が現在の二上神社、西が現在の三ヶ所神社です。
二上山は男岳と女岳の二つの岳が一つになっている山で、高千穂町と五ヶ瀬町にまたがっています。天孫降臨の峯としても伝えられ、三中にある乳ヶ窟(ちちがいわや)は、天照大神のお隠れになった岩戸とも、高千穂の伝説である鬼八の棲家だったともいわれています。
また、現在の境内は、伊弉諾尊と伊弉冊尊による、神生みの場所ともいわれています。
室町時代には、三田井右京大夫右武により再建され、江戸時代には炎上してしまいますが、その後再建されています。
明治4年には山附神社、明治34年には二神神社と改称され、昭和9年に現在の二上神社へと改称されました。
本殿の彫刻は高千穂町の有形文化財に指定されています。
境内の狛犬や石灯籠の猿の彫刻は、向山神社と同じく延岡の利吉という石工によるものです。
古くより、二上山信仰や日本神話と所縁の深い神社になります。
境内案内
こちらが二上神社の入口の鳥居です。両部鳥居になります。「そのまま車でお入り下さい。奥に駐車できます。」との案内も。また、階段を上るのが困難な方は右脇の道を車で、とも。

鳥居から真っ直ぐ参道を車で進みますと、その突き当りに石段です。なかなか長さのある石段です。

左右には石灯籠とその間に石祠です。左手の後ろには記念碑も。

こちらは右の灯籠と石祠です。

祠の中には石像らしきものも見えました。門守宮として、豊磐間戸命(とよいわまどのみこと)と櫛磐間戸命(くしいわまどのみこと)がお祀りされているものと思われます。

右の石灯籠の上には、神像らしきものが載っているのですが、残念ながら欠けてしまっています。おそらくこちらにお猿さんが載っていたのではないかと。

石段を上がります。両脇には大きな杉も聳えています。

ようやく半分ほど。

途中、踊り場がありまして、右手には小路とトイレです。

左手に建物。社務所でしょうか。

最後の石段を上がります。

拝殿前に到着です。

左右には狛犬さん。かなり変わった容姿の狛犬さんです。こちらが左。

こちらが右です。どことなくお猿さんのようにも見えます。

真横からの容姿も特徴的です。

狛犬さんの先、左手に手水石。お清めをします。

右には大きな杉や銀杏。

杉の前には授与所があり、その脇にも少し変わった形の、灯籠のような積まれた石がありました。

拝殿へと進みます。美しい拝殿です。屋根の妻飾り(懸魚)は牡丹でしょうか。

拝殿の右手前にご由緒書き。

参拝させて頂きます。

拝殿の中には、天孫降臨と国生みと思われる絵が左右に掛けられています。

拝殿を振り返りますと、こんな景色です。

授与所は閉まっています。

拝殿に向かって左手には、大きな杉といくつかの建物。

一番手前は神楽殿のようです。中には、御朱印や御守りがセルフサービスで置かれていました。初穂料はお賽銭箱に入れる形です。御朱印を頂きます。

こちらは拝殿を左斜め前から。美しい。

左手、一つ奥の建物は境内社の二上稲荷神社です。二上神社の旧拝殿とのこと。参拝させて頂きます。

二上稲荷神社の社殿内には、草花などの天井絵。その下は三十六歌仙のようです。

二上稲荷神社のさらに奥には、神輿庫のような建物。

境内の奥まで来ますと、本殿もよく見えます。本殿には精巧な彫刻が施されています。

上の鬼のような彫刻は、中国に伝わる道教系の神様で、厄除けや守り神として信仰されている、鐘馗(しょうき)様です。

脇障子には、少し変わった龍です。

周囲は杉の森です。山の中。

こちらは本殿の側から見た二上稲荷神社と神楽殿。

こちらは社殿の右手側。注連縄の掛けられた御神木のイチョウと、建物が二つ。

こちらが御神木の二上銀杏です。神聖な男女の持ち物が、自然に形とられているという御神木です。

しばし御神木を見上げて過ごします。

こちらは右斜め前から見た社殿。

境内の右奥にも小路がありましたので、許可さえあれば、ここまで車で来ることも可能ではあるようです。手前の建物は古神札納め所でした。

本殿の右側にも、精巧な彫刻。

上の彫刻は、天の浮橋を渡る伊弉諾尊と伊弉冊尊のようです。その前を鳥が飛んでます。

脇障子には花。

こちらは本殿側から見た御神木です。

参拝を終え、二上神社を後にします。石段は下りるときも慎重に。

参拝を終えて
この日4ヵ所目に訪れた二上神社。
まず、石段の下からの景色にやられました。新緑の季節ということもあり、綺麗な緑の中に長い石段が真っ直ぐ延びている景色は、それだけで惹かれるものがありました。
かろうじて下からでも拝殿の屋根が少し見えていましたが、それがもし見えなかったのなら、永遠に続いて行きそうな、そんな雰囲気もある石段でした。
僕たちはこの日、朝から既にそこそこ長い石段を何か所かで上っております。故に、中年の足腰にはじゃっかん疲労が蓄積されつつある時間帯です。そんなとき、この石段を前にして、不覚にも少々怯んでしまいました。
普段は石段がどれだけ長かろうが、全く気にせずに上がるんですけどね。
高千穂にて何度となく石段を上り下りし、この日はもうその三日目ですので、だいぶ弱ってきているのかもしれません。
しかし、当然ながら石段を上がること自体、楽しみな気持ちも大きいですし、こんな素敵なところを歩けるというのは、幸せなことでもありますので、嫁とともにゆっくりと上らせて頂くことに。
石段の下には参拝者用に杖も何本か置かれていたのですが、下手に慣れない杖を使うと転びそうな気もしましたので、杖無しで。
楽な石段ではなかったですけれど、その分上に到着したときの喜びは大きかったです。登山みたいなもんですね。
石段を上がるのが厳しい方は、鳥居の脇の道から、だいぶ上の方まで車で行くことができますので、どうぞ無理をなさらずに。
そして、石段の一番上、左右にいた狛犬さんのインパクトが強かった。
僕は初めて見るタイプの狛犬さんでして、かなり特徴のある容姿をしていました。どことなくお猿さんにも見える狛犬さんです。
正面から、横から、後ろからなど、色んな角度から観察させて頂きました。いいものが見れました。
残念だったのは、灯籠の上に載っているという猿の像を見つけることができなかったことです。石段下の灯籠の上に、おそらく何かが載っていたであろう跡はあれど、猿の姿は見えず。何があったのかはわかりませんが、欠けて失われてしまったのではないかと考えられます。
一つ前に訪れた向山神社にて、同じ石工さんの作による、石灯籠に載る猿は見れたんですけどね。
本殿の彫刻はばっちり見れました。特に左側の上、鐘馗様の彫刻がけっこう強烈に印象に残ってます。少し怖いくらいでしたし。
左側の脇障子の龍も、変わった容姿の龍でした。
本殿も拝殿も美しかったです。
御神木の二上銀杏には、伊弉諾尊と伊弉冊尊の国を作る営みを表す、アレとアレ(神聖な男女の持ち物、と説明されていました)が、自然と形とられた部分があるとのことですが、こことここかな?と少々曖昧な感じではありましたが、見させて頂きました。
また、このイチョウにはもう一つ言い伝えも。杖をついたご老人が長い石段をゆっくり上がり参拝したところ、突然体が軽くなり、杖がなくても歩けるくらい元気になり、そのまま杖を忘れて帰ってしまったそうです。で、いつしかその杖が根を張り、大きくなったのが、このイチョウだと。
この御神木のイチョウは大きくて立派でしたけれど、他にも大きな杉が何本も聳えていまして、その景色も素敵でした。
二上神社、参拝できてよかったです。
続いては、芝原神社へと向かいます。
御朱印
こちらが二上神社の御朱印です。

御朱印の受付時間
二上神社の御朱印は、拝殿に向かって左手にある神楽殿の中に、書き置きのもの(日付は自分で記入)が置かれていますので、初穂料をお賽銭箱に入れる形で頂けます。
(※ご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)
アクセス
住所は宮崎県西臼杵郡高千穂町押方2375-1です。
二上神社の公式サイトはこちらです。
https://www.hutagami.com/
駐車場
石段の下に2~3台駐車できます。

また、石段を上がるのが難しい場合は、石段の途中(かなり上の方です)の小路へと続く場所にも2~3台駐車可能です。鳥居の脇から上がって行きます。

トイレ
石段の途中にあります。

周辺のパワースポット
高千穂の神社巡り
高千穂の神社マップや神社巡りについては、こちらの記事でまとめてあります。
高千穂町の神社一覧
著者が参拝した高千穂町の神社の一覧です。