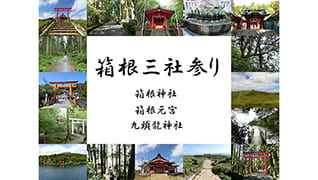藤沢市の江の島にある江島神社・奥津宮の参拝レポートです。
読み方は「えのしまじんじゃ・おくつみや」です。江島神社は、奥津宮、中津宮、辺津宮の三宮から成っていて、多紀理比賣命(たぎりひめのみこと)をお祀りする奥津宮は、かつては岩屋の本宮に海水が入り込んでしまう期間、御旅所として遷座していた地に鎮座しています。中津宮からは徒歩10分ほどです。
序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。
「江島神社・奥津宮」へ
この日は嫁と二人で朝から江の島にやって来ました。
前日には鎌倉の神社を巡り、一泊二日の小旅行です。
前日からかなりの急坂やら石段を上り下りしたため、僕は左の膝が思うように動かないという事態に…。一晩寝て治ったかと思ったのですが、江の島でも石段を上ったりしていますと、呆気なく再発してしまいました。
そんな状態ではありましたが、なんとか辺津宮、中津宮を回り、次の奥津宮を目指します。
江の島には三つの宮と、その先の海岸には岩屋という、江島神社発祥の地である洞窟があります。江の島の入口から岩屋まで順路通りに歩きますと、必然的に三つの宮を全て回り、最後に岩屋に到着するという形になっています。
僕は江の島には過去にも何度か来たことがあったのですが、神社に興味を持つようになってからは今回が初めてです。江島神社の御朱印を頂くのも初めてでした。
なんとなく神社を回るのと、興味を持って回るのでは、やはりそこには大きな差がありますね。興味を持って回った方が、見どころも色々発見できて面白いです。より楽しむことができます。
ですので、神社を訪れた際には、いつもできるだけ隅々まで境内を散策するようにはしています。それでも、僕も嫁も詰めが甘いので、大事なものを見逃してしまうことも多々あるんですけどね。
江ノ島には「エスカー」という有料のエスカレーターがありまして、それに乗ると比較的楽に中津宮までは回ることができます。乗らない場合は、それなりに階段を上らなければいけなません。
膝を痛めている僕にとっては、エスカーというのは救いの手のはずなのですが…先ほども書きました通り、神社ではできるだけ隅々まで散策したいんですよ。でもエスカーに乗ると、見逃してしまう場所がちょいちょい出てきてしまうんです。ですのでエスカーは使わずに、石段を上る羽目に。自業自得ですが。
既に左膝はかなりヤバくなっていて、おかしな歩き方にもなっています。
しかし、もちろんここまで来て引き返すわけにもいきません。
岩屋まではなんとしてでも行かなければ。
膝をかばいながら、奥津宮への道を歩き始めます。
ご由緒
江島神社全体のご由緒は、辺津宮の記事内で紹介していますので、こちらでは省かせて頂きます。
奥津宮のご祭神は、多紀理比賣命(たぎりひめのみこと)です。三姉妹(宗像三女神)の一番上の姉神で、安らかに海を守る女神といわれています。
奥津宮は、かつては本宮、もしくは御旅所(おたびしょ)と称されていました。岩屋に創建された本宮には、4月~10月の間は海水が入り込んでしまうため、その期間のみ遷座する御旅所として創建されたものになります。
社殿は壮麗を極めたといわれていますが、江戸時代の天保に焼失してしまい、その翌年に再建されたのが、現在の社殿になります。平成23年には本殿が改修されています。
拝殿の天井には、どこから見てもこちらを睨んでいるように見える「八方睨みの亀」が、江戸時代の絵師である酒井抱一により描かれています。
頼朝が奉納したとされる石鳥居もあります。
隣接する龍宮大神をお祀りする龍宮(わだつみのみや)は、平成5年に建立されたものになります。
境内案内
中津宮の参拝を終え歩き出しますと、すぐに右手にエスカー乗り場がありました。その先は長い石段になっています。

石段以外にはこれと言って何かあるわけでもなさそうでしたので、この日初めてエスカーに乗りました。やはり楽ちんですね。

エスカーを降りますと、かなり開けた場所に到着します。

少し歩くと、左手には海が展望できるレストランなどがあります。

その反対側、右手には展望灯台などがあるサムエル・コッキング苑です。今回こちらには寄らず、まっすぐ奥津宮を目指します。

その先、膝を痛めている人間にとりましては、なかなかキツい下りの石段です。雰囲気は素敵なんですけどね。

手すりと嫁につかまりながら、なんとか石段を下りますと、その先、左手に「江の島大師」です。

せっかくなので江の島大師にも参拝させて頂くため、立ち寄ります。

中には大きな不動明王さまがいらっしゃいます。とても静かで厳かな空間でした。

江の島大師では御朱印も頂きました。こちらが江の島大師の御朱印です。

江の島大師を出て、再び歩き始めます。

またしてもキツい下りの石段。頑張ります。

膝は痛かったのですが、その途中の景色が絶景でした。「山二つ」と呼ばれる場所です。

「山二つ」を越えますと、ようやく道が少し平らになり一安心。生しらすが美味しそうな食堂がたくさんあります。

生しらすの誘惑を振り払い進みますと、奥津宮が近づいてきたようです。

右手に奥津宮の手水舎が現れます。足元には亀がいるのも見えます。

手水舎には、足元だけではなく上にも亀がいました。水が出ていませんでしたので、手をはたいてお清め。

参道を進みますと、源頼朝が奉納した石鳥居です。

一礼して鳥居をくぐり、社殿へと進みます。

その手前、右に少し入った場所には御神木の銀杏がありました。手前には力石も。

さらに右の奥には、江戸時代の箏曲家(そうきょくか)、山田検校の像。

こちらが奥津宮の拝殿正面になります。辺津宮、中津宮とはまた雰囲気が違いますね。

拝殿前には特徴のある狛犬さん。こちらは左の狛犬さん。

こちらは右の狛犬さんです。どちらも毬を持っています。

奥には本殿が見えます。

拝殿には、龍と弁財天が描かれた、大きな杓文字が二つ。参拝させて頂きます。

天井を見上げますと「八方睨みの亀」がいます。確かにどの位置に移動しても、亀に睨まれているように感じますね。

奥津宮の参拝を終え、周囲を散策してみます。こちらは左斜め前から見た奥津宮の拝殿です。

奥津宮の隣には龍宮(わだつみのみや)があります。岩屋本宮の真上にあたる場所にあるそうです。御祭神は龍宮大神です。鳥居の先に大きな龍がいるのが見えます。

一礼して鳥居をくぐり境内へ。龍の迫力が凄いです。

参道の右手には手水鉢。少し変わった手水鉢ですね。

拝殿の手前には狛犬さん。こちらは左の狛犬さんです。

こちらは右の狛犬さん。どちらも龍に負けず迫力のある顔立ちをした狛犬さんです。

参拝させて頂きます。この龍は近くで見ますとかなりの迫力です。かっこいいです。

龍の周りを少し散策。龍宮は石垣のようになっていますね。

脇にあった御神木も素敵でした。一通り龍宮も散策し、境内を後にしました。

参拝を終えて
奥津宮の参拝を終えましたので、これで江島神社にある三つの宮には全て参拝したことになります。
三宮は同じ江島神社ではありますが、どれも雰囲気が全然違って、それぞれに魅力がありました。
奥津宮は、三つの中では最も静かに佇んでいる印象を受けました。二つ目の中津宮が鮮やかな朱の社殿でしたので、余計にそんなふうにも感じてしまったのかもしれません。
元々はこちら奥津宮が、本宮でもあったそうです。ご由緒のところでも書かせて頂きましたが、岩屋にある本宮に海水が入り込んでしまう4月~10月の間だけ、こちらに遷されていたとのことです。それが現在、奥津宮として岩屋とは別の形となってお祀りされるようになっています。
奥津宮には比較的新しく建立されました、龍宮が隣接していて、岩屋本宮の真上にあたる場所に鎮座しているとのこと。龍宮の上にいらっしゃる大きな龍が、かなり迫力がありました。
僕と嫁は、以前も江の島を訪れた際、こちらの龍がとても気に入ってしまいまして、龍と一緒に写真を撮ったのを覚えています。
龍の真下に立ちますと、迫力があるので少し怖い感じもするのですが、本物の龍に見つめられているようで、不思議な感覚にもなります。
奥津宮、龍宮とどちらも素敵なお宮でした。
また、奥津宮に向かう途中にありました、江の島大師もよかったです。中には大きな不動明王さまがいらっしゃり、その前に座ってみますと、静寂に包まれていて、無になれます。静かな時間を過ごすことができました。
一通りこのエリアを楽しみ、次はいよいよ江島神社発祥の場所である、岩屋へと向かうのですが…。
そこまでの道のりがまたキツいんですよね。以前に訪れた際にも、かなり急な階段を下った記憶がありますので。
果たして膝を痛めた僕は無事岩屋まで辿り着けるのでしょうか。
苦難の道は続きます。
御朱印
こちらが奥津宮の御朱印です。2019年5月より授与が開始されているものになります。

御朱印の受付時間
御朱印を頂ける場所は、辺津宮の左手にある授与所になります。受付時間は8時半から17時までです。
(※お時間やご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)
※江島神社では、頂ける御朱印が複数あります。以下の記事で詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
アクセス
住所は神奈川県藤沢市江の島2-6-15です。
江島神社の公式サイトはこちらです。
http://enoshimajinja.or.jp/
電車
①小田急江ノ島線 「片瀬江ノ島駅」から徒歩25~30分。
②江ノ島電鉄 「江ノ島駅」から徒歩30~35分。
中津宮から奥津宮までは10分ほど掛かります。少し距離があります。石段を下ったり上ったりもしなければいけません。階段が辛い方には少々辛い道のりかもしれません。
駐車場
江島神社の駐車場はありませんが、島内にはいくつか駐車場がありますので、そちらから徒歩での移動になります。江島神社の公式サイト内に駐車場案内がありますので、っご確認ください。
周辺のパワースポット
藤沢市の神社一覧
僕が参拝した藤沢市の神社一覧です。
江ノ島神社巡り
江ノ島の神社巡りについては、こちらの記事で全体をまとめてあります。