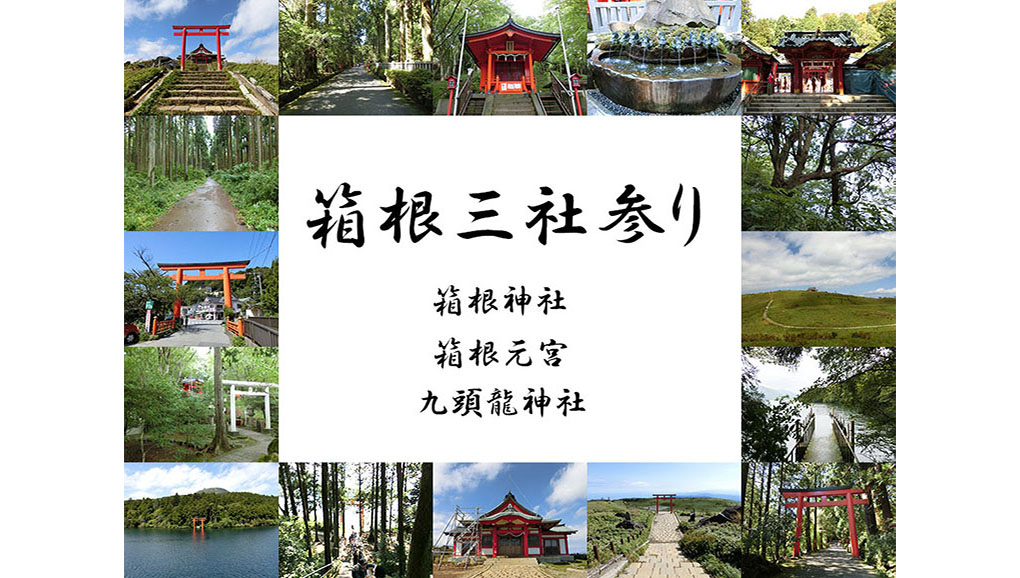文京区の千石にある巣鴨大鳥神社の参拝レポートです。
読み方は「すがもおおとりじんじゃ」で、正式名称は大鳥神社のみです。正確には「子育稲荷(こそだていなり)」と称される稲荷神社で、大鳥神社はその元境内社です。最寄り駅は巣鴨駅と千石駅になります。
序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。
巣鴨にある「子育稲荷」と「大鳥神社」へ
12月の初旬、雲一つない晴れ渡った空の下、巣鴨周辺の神社巡りに嫁とともに出掛けてきました。
正確には神社が三ヶ所、寺院が一か所の社寺巡りですね。一か所の寺院というのは、巣鴨の代名詞とも言ってもいい、とげぬき地蔵尊(高岩寺)です。三ヶ所の神社の方は、まず大塚駅からすぐの大塚天祖神、続いてそこから巣鴨寄りにある菅原神社。そして三ヶ所目に向かったのが、巣鴨駅の南にあります、こちらの記事で紹介する巣鴨大鳥神社です。
以前僕たち夫婦は、一日に10か所とか回る神社巡りをすることも、しばしばありました。回れるだけ回ってやろうと。
しかし最近は、4~5か所くらいがちょうどいいのでは?と思い始めております。10か所とか回るのは、それはそれで楽しいんですけどね。まぁその距離や内容にもよるかとは思いますけれど、やっぱ10って多いですよね。
それだけ歳を取ってしまったということなのか、悟ったのかは不明ですけれど。
朝のうちからスタートし、4~5か所巡って、その後はランチで美味いもんを食べつつ一杯やり、早い時間に帰宅するという、そんなコースがベストだと思う今日この頃。
この日も最後に参拝予定のとげぬき地蔵の近くには、以前も一度だけ訪れたことがある、「巣鴨ときわ食堂」というアジフライなどが美味しい定食の名店があるんですよ。前回食べたときも、とっても美味しかった覚えがあります。
ですので今日の締めは、アジフライでビールにしようかと。
そんなあれこれを考えつつ、二か所目に訪れた菅原神社より、大鳥神社を目指します。
巣鴨大鳥神社は、正式には稲荷神社なのに、境内社だった大鳥神社の社名で一般的にも称されるという、少々変わった神社でもあるようです。
巣鴨駅と大塚駅の中間辺りにある菅原神社からは、歩くこと10分ほどでした。
大きな白山通りに出る少し手前、路地の一角に、赤と白の鳥居を見つけました。
巣鴨大鳥神社に到着です。
ご由緒
ご祭神は、食物神である保食神(うけもちのかみ)です。宇迦御魂命(うかのみたまのみこと)や稲荷神(いなりのかみ)とも習合し、同一視されている食物や穀物の神様です。
創建は江戸時代中期の貞享の時代です。巣鴨村の新左衛門という人物が勧請し、稲荷社として創建したといわれています。
その後、隣接していた霊感院が別当寺となり、子育稲荷社と改称し、社殿を再建し、多くの参拝者が訪れるようになったそうです。江戸時代末期頃には、境内社の大鳥神社の酉の市も始められました。
明治になると神仏分離令により霊感院とは別れることとなり、霊感院は廃寺となります。
昭和には第二次大戦時の空襲により社殿が焼失してしまいますが、鬼子母神堂の近くに住んでいた武藤さんという人物が私財を投じ、昭和24年に再建しています。
昭和56年には、合祀していた大鳥神社を分祀し、新たに稲荷神社の社殿が造営され、現在に至ります。
大鳥神社のご祭神は、日本神話の伝説的な英雄である日本武尊(やまとたけるのみこと)です。
正式な社号は稲荷神社ではありますが、長らく続いている酉の市のためか、現在は大鳥神社として知られている神社です。
境内案内
こちらが大鳥神社の入口です。左が子育稲荷神社、右が大鳥神社の鳥居ですね。

どちらから参拝するべきか一瞬迷ったのですが、まずは左の子育稲荷から。

一礼して鳥居を二つくぐりますと、目の前が社殿です。

右には手水鉢。コロナにより使用禁止になっていました。

社殿前には神狐さんです。こちらが左の神狐さん。

こちらが右の神狐さん。少々怖いお顔です。

参拝させて頂きます。

子育稲荷の鳥居を出て、続いては大鳥神社の鳥居をくぐります。

前方の社殿は、少し高い位置に建てられています。

左手に手水舎。子育稲荷と兼用で、どちら側からでも使える仕様になっています。

拝殿へと進みます。

左手に社務所です。後ほど御朱印を頂きに伺ってみます。

社殿は白を基調とした建物です。大きくはありませんが、美しい。

右手に葉が全て落ちてしまったイチョウです。

石段を上がり、参拝させて頂きます。社殿の白と周囲の緑の色合いが素敵です。

拝殿には、蛇が彫られた石も置かれていました。

拝殿を上から振り返りますと、こんな感じです。意外と高い。

石段を下り、社殿の後ろ側にも回ってみます。

御朱印を頂くため社務所へ。呼び鈴を鳴らしましたが、残念ながらご不在のようでしたので、そのまま大鳥神社を後にします。

参拝を終えて
事前にこちらの稲荷神社と大鳥神社の関係は、なんとなく把握して訪れたものの、実際に境内の入口に立ちますと、さてどちらから参拝したものかと、一瞬迷ってしまいました。
元は大鳥神社が稲荷神社の境内社だったとのことですが、現在の様子ですと、どう見ても大鳥神社がメインで、稲荷神社が境内社みたいになってるんですよね。笑
ゆえに、どうしたものかと。
少々迷った末に、やはり見た目とのギャップは感じつつも、まずは稲荷神社から参拝させて頂きました。
しかしそんな迷いがあったのがいけなかったのか、稲荷神社を守る神狐さんのお顔がかなり怖く、怒られているかのように見えてしまって…。つい、ごめんなさいと言いたくなってしまったくらいです。
こちらのお稲荷さんは子育稲荷として親しまれているとのことですが、この近辺には「子育」や「子安」など、子供に関係した社名で称されている神社が多い気がします。この一つ前に訪れた菅原神社は子安天満宮とも称され、そこから西には池袋の子安稲荷神社もありますし。
こちらのお稲荷さんがなぜ「子育稲荷」と称されるようになったのか、その由来ははっきりとはわからなかったのですが、いずれにしても子育てや安産などにご利益があることは、間違いないと思います。
一方、大鳥神社の方は、境内の中央に鎮座しています。社殿は小さめなものではありますが、石段を10段ほど上がった高い位置に建てられています。社殿の周囲には緑があり、建物の白との調和が綺麗でして、清廉な印象も受けました。
石段を上がり拝殿の前にて振り返りますと、意外と自分が高い位置にいることに気付かされ、ちょっと気持ちよかったりも。
酉の市のときは、この境内だけにとどまらず、神社前の道路にもたくさんの露店が並び、多くの人で賑わうようです。
おそらくそんな酉の市の賑わいにより、いつしか稲荷神社との関係性が逆転していったのかもしれません。
そんなあれこれを思いつつ、参拝させて頂きました。
そして残念ながら、一つ前に訪れた菅原神社と同じく、こちらも宮司さんがご不在でして、御朱印を頂くことが叶いませんでした。
事前にご不在のことが多いとは認識していましたし、こればかりは仕方ありません。
潔く諦め、次の目的地へ。
続いては巣鴨の代名詞、とげぬき地蔵尊(高岩寺)へと向かいます。
御朱印
巣鴨大鳥神社には、御朱印があります。
しかし残念ながら僕たちはこのたび、宮司さんがご不在だったため、頂くことができませんでした。
御朱印の受付時間
御朱印と御守りを頂ける時間は、不定期です。ご不在のことも多いようですので、確実に頂きたい方は、事前の電話連絡(03-3946-7927)をお勧めします。平日よりは土日の方がいらっしゃることが多いようです。
(※ご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)
アクセス
住所は東京都文京区千石4-25-15です。
巣鴨大鳥神社の公式サイトはありません。
電車
①山手線/三田線「巣鴨駅」から徒歩5分。
山手線なら南口、三田線ならA1出口を出て、目の前の白山通りを、JRの駅を背にする形で進みます。右手に大鳥商店街と出ている路地を入って行きますと、右手にあります。
②三田線「千石駅」から徒歩5分。
A4出口を出て、目の前の白山通りを左に進み、左手に大鳥商店街と出ている路地を入って行きますと、右手にあります。
駐車場
参拝者用の駐車場はありません。近くにコインパーキングがいくつかあります。
周辺のパワースポット
文京区の神社一覧