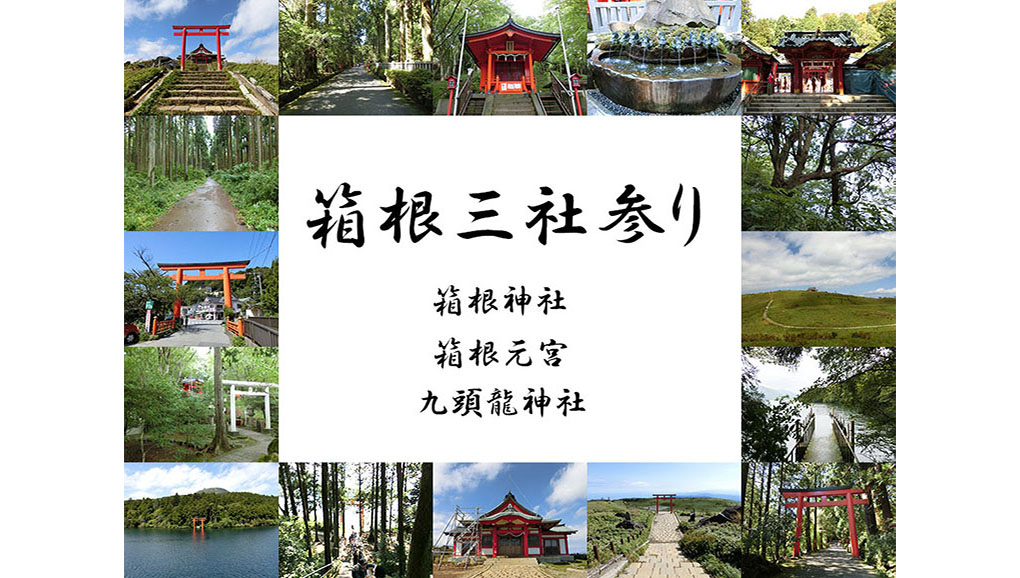鎌倉市にある佐助稲荷神社の参拝レポートです。
読み方は「さすけいなりじんじゃ」です。源頼朝に縁の深い神社で、古くからこの地に存在した「かくれ里の祠」を頼朝が探し当て、再建したといわれています。頼朝が後征夷大将軍にまでなったことから、出世稲荷とも称されています。鎌倉駅から徒歩20分。
序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。
鎌倉の「佐助稲荷神社」へ
紅葉の季節、鎌倉と江ノ島を散策しようと思い立と、一泊二日の日程で嫁と二人で出掛けてきました。
僕たち夫婦は、年に数回旅行に出掛けます。春夏秋冬と、それぞれの季節に一度くらいのペースです。
で、この秋の旅行先として選んだのが、鎌倉~江ノ島なのですが、その一番の目的といいますのが、こちらの記事で紹介する佐助稲荷神社なんですよ。
数ヶ月前でしょうか、嫁がどこかからか仕入れた情報で「鎌倉にある佐助稲荷神社の手ぬぐいが欲しい」と言い出しました。ネットでその画像を検索して見ると、赤地にたくさんの狐の顔が描かれている手ぬぐいで、確かに素敵なんですね。狐が皆違う表情をしていて魅力的でもあり、可愛くもあります。
ということで、旅の目的地が鎌倉になりました。
佐助稲荷神社を最優先の目的地として、旅行のおおまかなルートを練ります。
僕たちは4年ほど前にも鎌倉旅行をしたのですが、まだその頃は神社に特別な興味もなく、御朱印の存在すら知りませんでした。ですので今回は、神社巡りをするようになってからは初めての鎌倉です。なのでできれば鎌倉の神社も色々と巡ってみたいな~と。
しかし、鎌倉って神社も寺院もめちゃめちゃ多いんですよね、困ったことに。
どこを回るか、絞るのが難しいくらいに。
ですのでそこまで綿密な計画は立てず、とりあえず佐助稲荷に行ってみて、後は時間があったら近くの神社も回ってみよう、と緩い感じの計画にします。
そもそも、佐助稲荷神社自体、行くのが少々大変な場所っぽくはあります。最寄駅は鎌倉駅なのですが、徒歩で20~25分って書いてあるんですよね…。バスとかも近くまで行くのがないみたいで、かなり歩くようです。
タクシーという手段もなくはないですが、20分くらいでしたら歩いてしまおうと。歩くのは好きなので。
そして、地図を見ていたところ、鎌倉駅と佐助稲荷神社の間に諏訪神社があるのを見つけてしまいましたので、そちらにも立ち寄ってみることに。通り道のようなので。
鎌倉駅の西口を出発し、てくてくと歩くこと5分で諏訪神社に到着します。参拝を終え、再び佐助稲荷を目指し歩き始めます。
トンネルをくぐり5分ほど歩いたところに、佐助稲荷神社への案内図があり、そちらを右折。すると、住宅街の少し細い道になり、緩い上り坂が続いています。
僕たちと同じように、佐助稲荷神社を目指している人、もしくはその先にある銭洗弁財天を目指しているであろう人がたくさん歩いていました。修学旅行か遠足だと思われる、黄色い帽子の小学生もたくさんいました。
多くの人に交じり、僕と嫁も佐助稲荷神社を目指して歩きます。
ご由緒
ご祭神は、宇迦御魂命(うかのみたまのみこと)、大巳貫命(おおなむちのみこと)、佐田彦命(さるたひこのみこと)、大宮女命(おおみやのめのみこと)、事代主命(ことしろぬしのみこと)の五柱です。
宇迦御魂命は、食物や穀物の神様で、倉稲魂命とも表記され、稲荷神と同一です。 大巳貫命は、国造りの神である大国主命の別名です。佐田彦命は、道案内の神様で、猿田彦命と表記されることが多いです。大宮女命は、天照大御神に侍女として仕えたともいわれる、平安を守る女神です。事代主命は、大国主神の第一の息子で、託宣の神でもあります。
創建の年代は不明です。
古来より、この地を流れていた川の水源に、農業神として祀られていたともいわれています。
平安時代の末期、伊豆に島流しにされていた源頼朝は、三晩続けて同じ夢を見ました。夢の中では稲荷神がお爺さんの姿となり現れ、平家討伐の挙兵を勧めたそうです。
頼朝は平家と討伐した後、鎌倉時代前期の建久年間に、家臣の畠山重忠に命じてその「かくれ里の祠」を探し当て、稲荷神社を再建したのが当社です。
頼朝が幼少期に「佐(すけ)殿」と呼ばれていて、この「佐(すけ)」を「助けた」稲荷であることから、佐助稲荷と称されるようになったともいわれています。
別説では、上総介・千葉介・三浦介という「介」の付く三人の屋敷があったため、「三介ガ谷」と呼ばれていたのが変化していったとも。
長く鶴岡八幡宮の飛地境外末社でしたが、明治42年に独立し、現在に至ります。
『海街diary』など、映画やドラマのロケ地としても知られています。
頼朝が征夷大将軍にまでのぼりつめたことから、「出世稲荷」とも称され、信仰されている神社です。
境内案内
鎌倉駅の西口より、大きめの道路を真っ直ぐ西に進み、途中で右折して、住宅街の緩い上り坂を歩いて行きます。

住宅街に入り10分ほど進みんだところに、左折すると佐助稲荷、真っ直ぐ進むと銭洗弁財天と言う分かれ道があります。佐助稲荷を目指しますので、左折します。そしてさらに緩い上り坂を歩いて行きますと、佐助稲荷神社の幟が現れます。

まず到着しましたのが、佐助稲荷神社の下社になります。

社殿の脇にはご由緒書き。こちらには「縁結び十一面観世音菩薩」という菩薩様もいらっしゃいます。

まずは下社に参拝させて頂きます。

社殿の右手には、十一面観世音菩薩さま。もちろんこちらにも参拝。

下社への参拝を終え、さらに山の奥にある、佐助稲荷神社の本殿を目指します。

坂が少し急になってきました。朱色の鳥居が何重にも続いているのが見えます。

山へと続く赤鳥居。とても素敵な景色です。異空間へと続く道のようにも見えてしまいます。

鳥居をくぐりながら参道を進みます。これだけの数の鳥居の中を歩いていますと、現実感がなくなるような、不思議な感覚にも陥ります。

石段の途中には、何対かの神狐さんがいらっしゃいました。参道を護っているかのようです。

鳥居を全てくぐり終わると、さらに急な石段が現れます。

石段の手前にいた神狐さんが、少し大きくて特徴がありました。こちらは左の神狐さんです。足元には小さな神狐さんもいらっしゃいます。

こちらは右の神狐さんです。少し近寄りがたい雰囲気もあります。

急な石段を上ります。ここからの景色も素敵です。

石段を上り切った先、右手が手水舎です。両脇には神狐さん。

手水舎でしっかりとお清めを。

一礼して鳥居をくぐります。鳥居をくぐると目の前が拝殿です。

拝殿の手前、左右には大きな岩があり、こちらにも神狐さん。左のお狐さんです。少し変わった態勢をしています。

こちらは右の神狐さん。わかりづらいかもしれませんが、岩の真ん中にいらっしゃるのが神狐さんです。こちらも少し変わった態勢です。

拝殿へと進みます。

山の澄んだ空気の中、参拝させて頂きます。

参拝を終え、境内を散策してみます。いたるところに小さな神狐さん。

拝殿に向かって左回りで散策してみます。小路がさらに山の上へと続いています。

小路を上って行きますと、石鳥居です。

その先には、小さな石祠と小さな神狐さんがたくさん。神狐さん達の村みたいになってます。この一帯は、かなり空気が張り詰めている気がします。

完全に山の中。

さらに上へと登ります。少し上から先ほどの一帯を見るとこんな景色です。

けっこう険しい道を進んで行きます。

その先には、鳥居と大きな岩。「お塚」と呼ばれる場所です。こちらにも小さな神狐さんがたくさんいらっしゃいました。

お塚からさらに上へと登る険しい道がありましたので、登ってみます。かなり急な登り坂です。

息を切らしながら登って行ったのですが…その先には特に何もなさそうでしたし、このまま行くと遭難しそうでしたので…引き返すことに。写真は上から見たお塚です。

再びお塚の前を通り、坂を下って行きますと、また別の鳥居と少し社殿が見えてきます。

こちらは佐助稲荷神社の本殿でした。

本殿にももちろん参拝させて頂きます。たくさんの神狐さんが奉納されています。

本殿は、拝殿の裏手にある石段をまっすぐ上った場所に位置しています。こちらの写真は、本殿から拝殿の裏手を見た景色になります。

石段を下り、再び拝殿前に戻ります。拝殿に向かって右手が開けたスペースになっていて、社務所もそちらにあります。

社務所を越えてさらに右手の奥に進んだ先に、霊狐泉(れいこせん)。

とても綺麗な湧水です。霊狐泉とは、昔から麓の田畑を潤してきた水源で、霊狐の神水と称えられている湧水とのこと。こちらを持ち帰り、神棚にお供えするとご利益があるとか。

霊狐泉から拝殿を見るとこんな景色です。拝殿の右手には、ちょっとした休憩スペースもあります。

社務所で冷たいお茶が振る舞われていましたので、ちょっと一息。歩き回った後でしたので、美味しかったです。

一通り境内を散策しましたので、最後にこちらの社務所で御朱印を頂きました。そして念願の手ぬぐいも購入しようとしたのですが…残念ながら売り切れで既にありませんでした。

佐助稲荷神社を後にします。上から見る参道もとても素敵な景色です。幟旗と赤鳥居が綺麗ですね。

参拝を終えて
初めて訪れた佐助稲荷神社。
とても素敵な神社でした。
山の中にあり、「神域」という言葉がぴったり当てはまるような、そんな空気を纏っている神社でした。
まず、下社の先にある、赤い鳥居が続く参道がとても素敵です。異空間へ続く道のような不思議な参道です。
そして、連なる鳥居を抜けますと、いっきに空気が張り詰める感じがします。
境内には至る所に小さな神狐さんがらっしゃって、独特な空気が漂っていました。
拝殿を中心にぐるっと一回りできるのですが、見どころも色々あって、神聖な森の空気を吸い込みながらの散策はとても気持ちよかったです。
しかしながら、足を踏み入れてはいけないのでは?と思ってしまうような雰囲気の場所もあり、そういった意味では緊張感もありました。
お塚と呼ばれる場所からさらに山の中へと道が続いてましたので、興味本位で途中まで登ってみたのですが…かなり険しい道でしたし、本当に遭難するかもしれない、と不安になって引き返しました。後から調べたところ、どうやらそのまま進んだ先は、大仏ハイキングコースなる道へと繋がっていたようですね。
境内全体が神聖な空気に包まれているようで、とても心に残る神社でした。
霊狐泉と言う湧水も素敵でした。
そして、何よりこの神社に来るきっかけとなった、嫁のお目当ての手ぬぐい。
まさかの売り切れだったんですよ…。
実は、嫁の妹さんからも購入を頼まれていまして、二枚買う予定だったんです。それが授与所で売り切れだと聞かされ、残念がる嫁。こればかりは仕方ありません。
しかし、そこで神の一声。
宮司さんのご自宅に、最後の二枚があるとのこと。そしてなんとそれを郵送してくださると。
そんなご対応をして頂いてよいものか迷いはしましたが、ご厚意に甘えることにしました。
その場で手ぬぐい代を納め、住所を書きました。
こちらが後日送ってくださった佐助稲荷神社の手ぬぐいになります。

宮司さんの奥さんが大事に持っていたとおっしゃっていましたので…大切に使わせて頂きます。
ご厚意に感謝です。本当にありがとうございました。
御朱印も頂き、手ぬぐいも後日送って頂けることとなり、ありがたいこと尽くしの参拝を終えた僕と嫁。
佐助稲荷神社、参拝できてよかったでsy。
続いては、そこから近い場所にある、銭洗弁財天宇賀福神社へと向かいます。
御朱印
こちらが佐助稲荷神社の御朱印です。

御朱印の受付時間
御朱印と御守りを頂ける時間は、10時から16時までです。ただし、ご不在のこともあるようです。
御朱印は書き置きのものとなります。御朱印帳に書いて頂きたい方は、こちらで朱印のみ押して頂き、長谷寺の近くにある「御霊神社(ごりょうじんじゃ)」にて墨書きをして頂けます。詳しくは公式サイト内のトピックスのページに御朱印の案内がありますので、そちらをご確認ください。
(※お時間やご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)
アクセス
住所は神奈川県鎌倉市佐助2-22-12です。
佐助稲荷神社の公式サイトはこちらです。
https://sasukeinari.jp/
電車
JR / 江ノ島電鉄 「鎌倉駅」から徒歩20~25分。
鎌倉駅から徒歩ですと、それなりに距離があります。近くまで行くバスもありませんので、歩くのが厳しい方は、タクシーでの移動をお勧めします。タクシーでも入口までしか行けません。後は石段を上ることになりますので、ご注意ください。
駐車場
参拝者用の駐車場はありません。少し駅寄りにコインパーキングがいくつかありますので、そちらに駐車してあとは徒歩という形になります。
周辺のパワースポット
鎌倉市の神社一覧
僕が参拝した鎌倉市の神社一覧です。