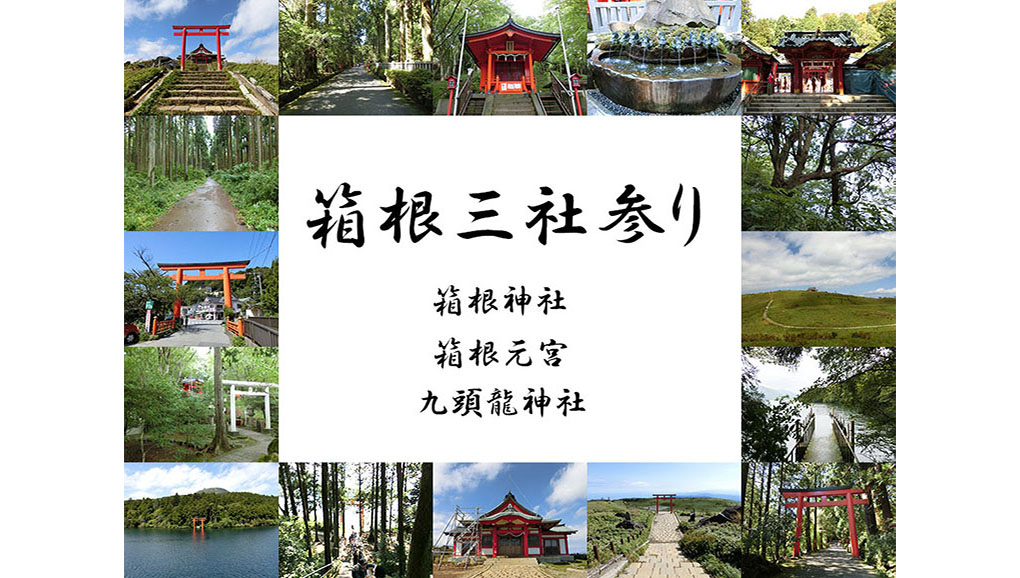武蔵村山市の初詣のご案内です。市内の各地域ごとに、初詣にお勧めの神社を一覧で紹介しています。
初詣は大きな神社に出掛けるという方も多いとは思いますが、ご自分の住んでいる地域を守ってくださっている神社(氏神さま、産土さま)に参拝することも大切です。
氏神さまに、前年を無事に過ごすことができた感謝をお伝えし、新年のご挨拶と平安の祈願をしましょう。
武蔵村山市の神社マップ
それでははじめに、武蔵村山市にある神社を地図で一覧にしていますので、参考にして頂ければと思います。
武蔵村山市内の比較的大きめな神社のみ掲載しています。
上記が武蔵村山市にある全ての神社ではありません。小さな神社や祠など、実際にはさらに多くが存在しています。
また、こちらの記事では神社のみの紹介で、寺院は掲載しておりませんので、ご了承ください。
次項より、武蔵村山市内の神社を、それぞれのエリアごとに、ざっくりな説明と併せて紹介していきます。
中藤・神明の初詣
中藤八坂神社
創建の年代は不明ですが、江戸時代後期にはその名が記されていることから、それ以前であると考えられています。境内には「立皮(たてかわ)の桜」と呼ばれる名木があります。多摩湖の南にあり、最寄の上北台駅からは徒歩で20~25分ほどです。(武蔵村山市中藤5-86-1)
中藤熊野神社
小名谷津の鎮守です。創建の年代はわかっていません。明治になり愛宕神社を合祀して、鎮守となったと伝えられています。境内には、大きな砲弾の形をした日露戦役紀念碑があります。多摩湖の南西にあり、最寄の上北台駅からは徒歩で25~30分です。(武蔵村山市中藤3-23-1)
神明ヶ谷戸神明社
神明ヶ谷戸の鎮守です。創建の年代は不明ですが、かつては遥拝所だったものを、鎮守としたといわれています。現在、神明自治会館としても利用されています。多摩湖の南西、上北台駅からは徒歩20~25分です。(武蔵村山市神明2-86)
入り天満宮
創建の年代は不明です。かつては近隣にある真福寺というお寺が所有していた天満宮が、明治の神仏分離により、八幡社、稲荷社、水天宮を合祀して独立し、現在に至ります。大曲り新道と中砂新道の交差点近くにあります。(武蔵村山市中藤1-50-1)
中央・榎・学園・大南の初詣
お伊勢の森神明社
江戸時代中期に伊勢神宮のご分霊を勧請して創建された神社で、中藤・横田両村の総鎮守です。境内には樹齢400~500年といわれる巨大な杉が聳え、「おい伊勢の森」と称されてきました。新青梅街道沿いに鎮座しています。(武蔵村山市中央2-125-1)
原山神明社
元々は、お伊勢の森神明社の遥拝所だったといわれています。江戸時代の末期には、陰陽師である指田家が神主を務めていました。小名原山の鎮守でもあった神社です。お伊勢の森神明社の北、青梅街道の少し先にあります。(武蔵村山市中央3-70-1)
日吉神社(中藤日吉神社)
創建の年代はわかっていません。かつては山王権現や山王社と称され、江戸時代には山王様と称され親しまれていたそうです。御神体は、三ケ島にあった昌明院というお寺より遷されたものになります。大曲り新道から少し入った場所にあります。(武蔵村山市中央4-1)
残堀・三ツ藤・伊奈平の初詣
残堀神明社
旧三ツ木村峰地区の人々が、この地域の新田開発のために入植し、その際に元の村にあった神明社を遷座し、鎮守とした神社です。元の創建年代などはわかっていませんが、遷座したのは江戸時代の前期になります。(武蔵村山市残堀5-29)
本町の初詣
七所神社
横田地域の鎮守です。創建の年代はわかっていませんが、かつては七所社と称されていたそうです。明治になり、近隣にあった愛宕社、八幡社、諏訪社、八坂社の四社を合祀し現在に至っています。伝統的な横中馬獅子舞が立ち寄る神社の一つでもあります。野山北・六道山公園の東にあります。(武蔵村山市本町5-11-2)
熊野神社(中村熊野神社)
中村地区の鎮守です。創建の年代はわかっていませんが、江戸時代以前です。五穀豊穣や無病息災を祈願して行われる、伝統的な横中馬獅子舞が立ち寄る神社の一つでもあります。多摩大橋通り沿いにあります。(武蔵村山市本町4-16-2)
八坂神社
馬場地域の鎮守です。元は大行院というお寺の境内に祀られていて、江戸時代には牛頭天王社と称されていました。明治の神仏分離により、現在の八坂神社となりました。伝統的な横中馬獅子舞が立ち寄る神社の一つでもあります。野山北・六道山公園の南にあります。(武蔵村山市本町3-48)
三ツ木・中原の初詣
十二所神社
飛鳥時代から奈良時代にかけての創建と考えられている、大変古い神社になります。旧三ツ木村の鎮守です。三ツ木という地名は、こちらの境内にあった三本の木に由来しているともいわれています。かつては幹回りが4メートルのツガの木があったそうです。野山北・六道山公園の南、上北台駅からバスで5分ほどの場所にあります。(武蔵村山市三ツ木5-12-6)
赤稲荷神社
青梅街道沿いにある小さな稲荷神社です。江戸時代の後期に創建され、元は屋敷神だったと伝えられています。(武蔵村山市三ツ木3-23-2)
峯守稲荷神社
十二所神社のすぐ西にある小さな稲荷神社です。創建の年代や経緯などは不明です。(武蔵村山市三ツ木5-11)
岸の初詣
須賀神社
岸地域の鎮守です。江戸時代の中期に創建され、岸の天王様と称され親しまれてきた神社です。昭和になり近隣のいつくかの神社を合祀し、現在に至ります。野山北・六道山公園の西にあり、最寄駅は箱根ヶ崎駅になります。(武蔵村山市岸2-24-3)
隣接地域の神社
お住まいの地域によっては、武蔵村山市と隣接する・立川市・福生市・東大和市・瑞穂町・埼玉県所沢市の神社の方が行きやすい場合もあるかと思います。
周辺地域の初詣にお勧めの神社についても、下記にそれぞれリンク記事を貼っておきましたので、是非チェックしてみてください。
・埼玉県所沢市(未作成)