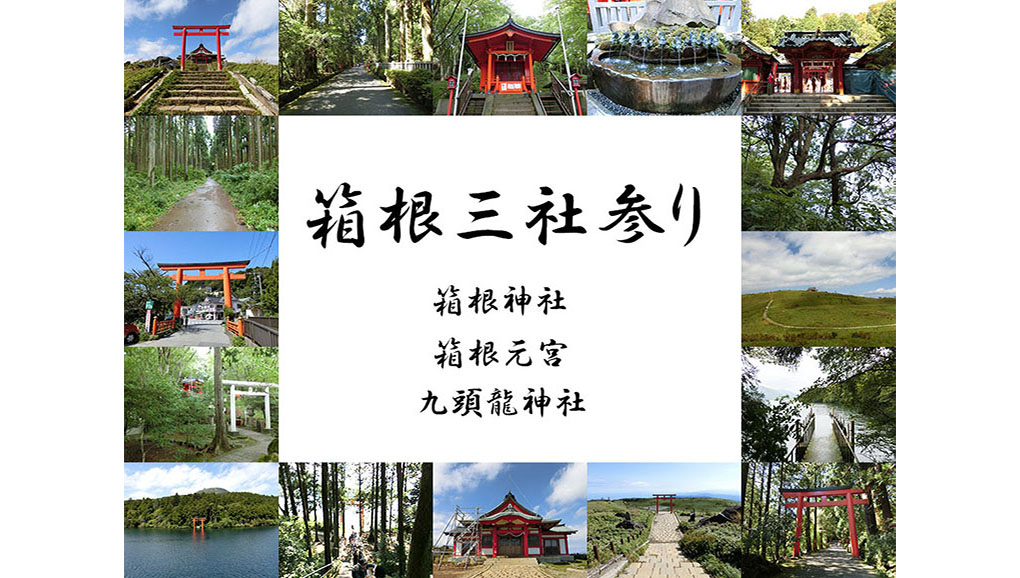目黒区にある上目黒天祖神社の参拝レポートです。
読み方は「かみめぐろてんそじんじゃ」です。正式名称は「天祖神社」のみになります。かつては伊勢森と呼ばれた地に鎮座し、境内には樹齢数百年と推定される樹木が多く残されています。中目黒駅と祐天寺駅の中間辺りに位置しています。
序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。
上目黒の「天祖神社」へ
上目黒天祖神社は、この日訪れる三ヶ所目の神社です。この参拝を終えたら、今日の神社巡りは終了し、帰路に就く予定です。
最初に訪れたのは、代官山にある猿楽神社です。猿楽塚という古墳の上に建つ神社で、小さな神社ではありましたが、気持ちよい時間を過ごさせて頂きました。
次に訪れたのが、代官山の一つお隣、中目黒が最寄の中目黒八幡神社です。境内には大きな木がたくさん茂っていて、緑の多い神社でした。同じくこちらでも、気持ちよい時間を満喫させて頂きました。
この神社巡りは、僕たち夫婦にとってかなり久しぶりのものになります。
僕が2月に肺の手術をしまして、その前後は出掛けられなかったことに加え、コロナウィルスが日に日に猛威を振るってきましたので、その危険を考えますと、外出を控えざるを得なかったりもしました。
そんな中ではありましたが、嫁の用事が代官山でありましたので、それに合わせる形で、おもいきってこの度お出掛けをするに至りました。もちろんコロナにはじゅうぶん気を付けつつです。
手術後初の神社巡りにもなりますので、僕の体力と相談しつつ、という感じでもあります。
一ヶ所目の猿楽神社から二ヶ所目の中目黒天祖神社までは、少々距離がありましたが、特に問題なく歩けました。息切れもせず体力も大丈夫そうです。
次に予定していた上目黒天祖神社は、中目黒八幡神社から、地図を見る限りはそんなに遠くなさそうです。体も問題なさそうですし、距離も近そうですし、予定通り向かうことにします。
手術直後はすぐ息切れしてしまって早く歩けなかったり、疲れやすかったりしたのですが、それも時間とともに回復していきました。こうしてまた神社巡りができるということが、普通に歩けるということが、本当に幸せです。
コロナウィルスの影響で、次はまたいつこうして散策できるかわかりませんので、久しぶりの嫁との散歩も存分に楽しみつつ、歩きます。
中目黒八幡神社から、歩き出して5分掛からないくらいだったでしょうか。
少し大きめの道路に出てすぐ、石鳥居が目に入りました。
上目黒天祖神社に到着です。
ご由緒
ご祭神は、日本国民の総氏神で、皇室の祖とされる神様である、天照大神(あまてらすおおみかみ)です。太陽を神格化した神様ともいわれています。
創建の年代は不明です。古くより伊勢森と呼ばれたこの地に、神明社として鎮座していたと伝えられています。境内には樹齢数百年と推定される樹木が多いことから、創建もかなり古い時代ではないかと考えられています。
江戸時代中期の庚申塔が二基あり、そのうちの一基はかつては道標をかねていたものといわれています。どちらも目黒区の指定文化財です。
現在の社殿は昭和8年に建立されたものになります。
古くより、この地域の人々に崇敬されている神社です。
境内案内
こちらが上目黒天祖神社の入口です。鳥居のすぐ向こうにはトラックが駐車していて、工事かな?と思ったのですが、その先にも車が並んでいましたので、どうやら駐車場になっているようです。

左手前には社号碑。

本来は鳥居をくぐって参道に足を踏み入れるべきなのですが、トラックでくぐれず、やむを得ず隣接する路地を進みます。参道には車がびっしりと停まっていました。こういう形の駐車場は初めて見ました。

参道脇を進みます。前方には大きな木、その向こうには手水舎も見えてきました。

駐車場スペースを通り過ぎ、ようやく参道に。境内には立派な木が何本か聳えています。正面に社殿です。

玉垣の手前、左手に御由緒です。

歩を進めます。境内はけっこう開けています。

左手に二基の庚申塔が見えましたので、後ほど行ってみることに。

まずは参拝のため、参道をまっすぐに。

右手には神楽殿です。その向こうが隣接して社務所になっているようです。

左が手水舎です。手水舎の後ろにあるイチョウの木が、ひときわ大きいです。

お清めをします。手水石が変わった形をしていました。

拝殿へと向かいます。社殿はそんなに大きな建物ではありません。シンプルな社殿です。

一度足をとめて、手水舎の後ろにあったイチョウを振り返ります。

しばしイチョウを見上げてから、拝殿へ。

社殿は昭和8年に造営されたものとのことです。

時間を掛けて、参拝させて頂きます。

境内を少し歩いてみます。こちらは社殿を左斜め前から。奥には本殿も見えます。

左手の奥にはもう一つ鳥居がありました。裏参道ですね。その向こうは公園になっているようです。

こちらは社殿を右斜め前から。

右手奥の社務所へ。閉まっていて人の気配はありませんでした。

社殿の右奥に神輿庫がありまして、中のお神輿を見ることができます。

手水舎の奥にあった、二基の庚申塔にもお参りさせて頂きます。庚申塔にはどちらも三猿が彫られていました。

脇には庚申塔の説明書きもありました。右の庚申塔が、かつて道標にもなっていたものだそうです。

一通り境内を散策し、上目黒天祖神社を後にしました。

参拝を終えて
この日三ヶ所目に訪れた上目黒天祖神社。
最初から最後まで、僕と嫁しか人がおらず、のんびりと参拝させて頂きました。
境内には目を惹くものがいくつかあったのですが…一番インパクトが大きかったのが、参道に駐車された車たちです。
鳥居の先、参道をふさぐかのようにトラックが停まっていて、まずその景色にびっくりしたのですが、その先にも同じように車が並んで停められていて、月極の駐車場であることを理解しました。
境内に月極の駐車場がある神社は、少なからずあるかと思います。僕もこれまでにも何度か目にしております。参道の両脇がそのような形になっているとところもありました。
しかし、参道を完全にふさいでしまう形の駐車場というのは、こちらで初めて目にしましたので、ちょっとした衝撃でした。
参道をふさいでしまうというのは、おそらく神社側としても、運営のための苦肉の策だったのではないかと、そんなふうには思うんですけどね。
お祭りのときとかどうするのかな?と疑問に思い調べてみたところ、どうやら例大祭のときは車を停めないという契約で、駐車場として貸しているみたいです。
それぞれの神社の事情があると思いますので、部外者があれこれ言う筋合いは全くありませんが、純粋にちょっとびっくりはしました。
もちろん、鳥居をちゃんとくぐって参道を歩き、お参りはしたいですけどね。駐車場にしなかったら、神社の存続自体が危ういかもしれないってことだと思うので。むしろどんな手段でも、神社を維持してくださっていることに、感謝しないといけないのかもしれないです。
すみません、ついつい参道の駐車場についてばかり書いてしまいましたが、境内にはもちろん素敵なものもありました。
立派な木が何本も聳えていまして、中でも手水舎の後ろにあったイチョウの木は、ひときわ大きくて目を惹きました。
手水石も少し変わった形のものでしたね。
社殿はシンプルな造りではありますが、古さゆえか、とても落ち着いた雰囲気がありました。
二基の庚申塔にも、しっかりと手を合わさせて頂きました。右側のものは、もともとは神社前の通り際にあり、「右に行けば世田谷、左に行けば目黒不動」という道標だったみたいですね。
こちらの神社は、本務社が同じ目黒区内の烏森稲荷神社というところでして、御朱印はそちらで頂けるようです。また機会を作って、烏森稲荷神社にも足を運んでみようと芋います。
上目黒天祖神社を後にして、久しぶりの神社巡りが終了です。
次に神社巡りに出掛けられるのはいつになるのか。コロナが落ち着くまではしばらくお預けになりそうです。
一日も早いコロナウィルスの終息を願っています。
御朱印
上目黒天祖神社の御朱印は、同じ目黒区内にある烏森稲荷神社が本務社となっていて、そちらで頂くことができます。
僕はまだ烏森稲荷神社に参拝しておりませんので、頂きましたら追記で掲載させて頂きます。
(※ご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)
アクセス
住所は東京都目黒区上目黒2-32-15です。
上目黒天祖神社の公式サイトはありません。
電車
①東急東横線/日比谷線 「中目黒駅」から徒歩10分。
東口2から構外に出て、右に進みます。道路に出たら左折し、そのまましばらく真っ直ぐ。駒沢通りにぶつかったら右折。少し歩いた右側です。
②東急東横線 「祐天寺駅」から徒歩10分。
東口1を出て、ロータリーの先、祐天寺駅通りをまっすぐ進み、駒沢通りに出たら左折。しばらく歩いた左側です。
駐車場
参拝者用の駐車場はありませんが、境内に少しでしたら駐車できるスペースがあります。参道の駐車場は月極ですので駐車できません。また、すぐ近くにコインパーキングもあります。
周辺のパワースポット
目黒区の神社一覧